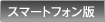知事記者会見の概要(令和6年7月19日(金))
令和6年7月19日(金曜日)
10:30~12:00
県庁 特別会議室

[知事]〔配付資料:ふくいはぴコインの常時チャージについて〕
まずは、「ふくいはぴコイン」ですが、常時チャージを始めるということで、本日からこの機能をスタートさせていただいたところです。今までも、例えばプレミアム付き商品券であったり、ふく+(ふくたす)や、ふくいdeお得いこーよ!キャンペーン、省エネ家電キャンペーンの時に、「はぴコイン」を使ってポイントをもらうことができたのですが、みなさんからチャージができないのは非常に使い勝手が悪いというふうに言っていただきました。PayPayや楽天ペイなどいろいろなものがありますが、こういった常時チャージができる機能を追加させていただきました。
チャージの方法はよく他でもありますが、クレジットカードやセブン銀行やBankPayなど、こういうものを使って上限3万円まで入れられるということです。このチャージの特典としまして、まず一つは入金の際にもそれから使う際にも、利用者のみなさんには手数料がかからないこと。ここのところはふくいのデジタルという会社が運営していますので、そちらの方で負担をしていくと。その上で今回、夏休み期間中というのを念頭に置きながら、例えば5000円以上チャージして5000円以上利用したら、ポイントがもらえるということであったり、iicaJCBカードでチャージをされた方は別途5000ポイントが当たるキャンペーンも行わせていただきます。
特にこの「はぴコイン」については、秋以降ですが、ご当地クーポンということで、単にポイントだけではなくて、特別な体験や、裏メニューなどこういうことにも活用ができますので、他のPayPayなどとは少し違い、お金以外にも活用範囲が広がっていくということかと思っています。
続きまして二点目ですが、北陸新幹線について敦賀での乗り換えが不便だということは、事前から予想もされていましたので、これを予算の段階から、乗り換えの時に色々と情報を楽しんでいただくことや、またワクワクできるような体験ということを検討してきました。その中で、この「乗り換えわくわくキャンペーン」というのを実施させていただきます。8月中を目途としまして、基本的には新幹線から降りて在来線に乗り換えるところ、改札口があるところのあたりを通過する、もしくはあの二階から少し半二階のところ降りるように通過しますと、ここにありますがJR西日本のWESTERアプリをダウンロードし、アプリを起動しておいて位置情報とBluetoothをオンにしていただいた方で画面を出しておいていただくと、そこを通過しますと抽選券がここに届くと。届いたら、電車に乗っていただいた後で、それを見て応募していただくというか、ボタンを押せば即時そこで抽選が行われまして、1000円分の「はぴコイン」が当たったりするということです。これを県内の4401店の取扱店で商品に変えていただくということで、乗り換えることを楽しくしようということになっているところです。これについて特徴としましては、移動するだけでいい。ボタンを押すとかQRコード取るとかをやるととても時間がかかったりして混んだりしますので、そういうことはなく、移動すれば届くということです。それから県内外、そこを通る人みんなが参加できる。すぐに結果が分かる。それから可愛らしい福井県内のゆるキャラが当落を発表してくれる。こういうところでして、ぜひ多くの方に敦賀駅を利用いただきたいと思っています。
[知事]〔配付資料:救急医療電話相談事業(#7119導入、#8000拡充)について〕
続きまして「#7119」の運用開始などについてお話をさせていただきます。
特に夜中などに具合が悪くなったような場合に、119番通報される方は結構いらっしゃると思います。ただ現実には119番通報を受けた場合、2割程度は「どこか病院は開いていますか?」といういわゆる相談事項であったり、もしくは実際に運ばれていく場合でも、都会などのお話を聞きますと半分以上が軽症で、言ってみれば翌日行けば十分に間に合ったというようなことが多いと伺っています。
救急も福井県内は都会ほどではありませんがそれなりに逼迫をしてきていますので、できるだけ必要な人をすぐに救急車で運べるようにしていくことが重要だということで、福井県でもこの「#7119」の運用を10月1日から始めることにさせていただきました。
運用時間は24時間365日でして、いつでも電話を「#7119」にかけていただけます。119番って結構かけるのも勇気がいると思います。本当に苦しんでいればすぐにかけられると思いますが、どうなのかなという時に、この「#7119」にご連絡をしていただきますと、看護師が出てきて「それはすぐ119番にしましょう」ということなどに繋がっていくわけですし「まあ、少し様子を見ましょうか」ということも出てくるわけです。
その子ども版が「#8000」でして、これについては、すでに平成17年度から運用をさせていただいているところです。これを運用していますと、基本的には病院が開いている時間帯は病院や小児科さんなどに行っていただこうとしていて、閉まっている時、基本的には19時から翌日の9時までを運用時間としてきたところですが、土曜日は午後半休ということが結構病院の場合もあるものですから、この午後の時間帯を開けてほしいということがありましたので、この土曜日の13時から19時を新たに電話相談の対象時間帯にするということを10月5日から始めさせていただこうというものです。
私からは以上です。
~質疑~
[記者]
「ふくいはぴコイン」のチャージ機能とキャンペーンということですが、直近で登録者がどのぐらいいるのか。また、今回の新たな取り組みによる「ふくいはぴコイン」の普及拡大について知事はどのように期待されているかをお伺いしたいと思います。
[知事]
「はぴコイン」は、登録していただいている方が16万2千人ぐらいと伺っています。これまでの実績として、「はぴコイン」で15億円ぐらいの消費活動が行われたと伺っています。そして県内のお店で、使える場所が4401店舗と聞いています。これをどれだけ広げるかといいますと、今回はみなさんからもっと使いやすくしてほしいとも言われていますので、これを拡大することで、さらに多くの方にPayPayのように使っていただけると期待をしています。ふく割は、40万ダウンロードに近かったということもありますが、あれは次から次へと企画というかメリットがあったということですが、「はぴコイン」はなんといってもキャッシュレスでいろいろお買い物ができるということだけではなくて、先ほど申し上げましたようないろいろな特典をつけることで、県民の行動変容にも繋げていくというような大きな目標もあります。消費活動を喚起するという部分と、行動変容を促すという部分の両面で活用されるように、さらにいろいろなキャンペーンなどを通じて拡大していきたいと思っています。
[記者]
「#7119」の導入について伺います。これは全国でどれくらいの県の数・地域の数のうち何番目となるのでしょうか?
[知事]
25の都府県と5つの市だと伺っていますので、その次ということになるかなと思っています。
[記者]
「はぴコイン」についての確認ですが、手数料なしとは、特典の期間以外もずっと手数料はなしということでしょうか?
[知事]
遠い将来までは分かりませんが、現状そういう予定です。
[記者]
先ほど知事もおっしゃっていたかと思うのですが、「はぴコイン」は、ふく割のアプリよりまだ県内の認知度が低いのではないかな、使っている方が偏っているといいますか年配の方には難しいのかなという印象もあるのですが、その辺はいかがでしょうか。
[知事]
難しさがそう上がっているという雰囲気ではないと思いますが、使う機会をふく割と比べたときに、ふく割は次から次へと、しかも結構なメリットのあることがどこでも使えるというのがいつも出ていたので、使い勝手といえば、PayPayなどを使っていらっしゃるような世代が中心になるのかなとは思っています。
とはいえ、「はぴコイン」には、先ほどからも申し上げているように、一か月何歩歩いたら1ポイントだとか、ボランティアやったら何ポイントもらえるとか、もしくは県内のこんな企画に参加できるというような、お金に換算できないもの、もしくは行動変容に結びつくようなことにも活用ができるというメリットがありますので、そういったところも広くPRしながら拡大していき、何かの時にはこれを使ってすぐにお金が動くというような、例えば妊娠出産の時には5万円のところを5%上乗せして、「はぴコイン」でお支払いするという方法もありますので、こういったことにも活用できるようにしていきたいと思っています。
[記者]
次に「乗り換えわくわくキャンペーン」についてお聞きしたいのですが、そもそも敦賀駅の乗り換えの不便さというのは、連絡通路のところにICのタッチの機能がなく、せっかくの連絡通路があるにも関わらず、また敦賀のハピラインの駅まで戻っていかなくてはいけないというような不便さ、少し複雑な構造の故の不便さがあるかと思います。このわくわくキャンペーンについてはわからないこともないのですが、実際の不便さ自体が解消されたわけではないとは思います。その辺はいかがでしょうか。
[知事]
以前から申し上げているようにJR西日本さんには、乗り換え改札ではICOCAなどの印が入るようにしてもらうことや、できれば紙の切符を欲しいという方もいらっしゃるので、券売機そのものを乗り換える場所のところに置いていただけないかということをお願いしているところです。これはこれとして、私としては、長谷川社長などに直接お願いする機会を作りながら、できるだけ不便なところを解消していくことに力を注いでいきたいと思っています。
その上で、先ほども申し上げましたが、いずれにしても当分の間、乗り換えは必要なので、少しでも乗り換えることを楽しんでいただくこととして、こういったキャンペーンをしていきたいと思います。今後もデスティネーションキャンペーンや来年の3月には一周年という時期も来ますので、いろいろなタイミングで、乗り換えを楽しんでいただくことをしていきたいなと思っています。
[記者]
「ふくいはぴコイン」の常時チャージ機能についてお伺いします。この資料の一番上にも書いてありますが、ふくいのデジタルの協力によりと書いてあるんですが、先日福井県が県内企業と初めてDX推進に関する協定をふくいのデジタルと締結したと承知しておりますが、その取組みの一環、第一弾という認識でよろしいでしょうか。
[知事]
ありがとうございます。まさにそうだと思っております。このことは、やっぱりふくいのデジタルさんの側から言うと、コストがかかる部分ですので、どうしても入金する時、それからお店との間のところで通常であればコストがかかるということですので、そこのところを負担していただきながら運営していくということにつながるわけですので、話し合いの中でふくいのデジタルさんにご理解をいただいて、それで我々がやろうとしていることの趣旨もご理解をいただいた結果と認識をしていますので、こうした取り組みをぜひ他のところにも、DXを広げていけるようにもしていきたいと思っています。
[記者]
いまご説明ありました通りかもしれませんが、今回のこのキャンペーンも含めて、このチャージ機能の機能拡充など、そういったものにかかった費用は、県として負担は生じていないという理解でよろしいでしょうか。
[知事]
はい。こういうシステムの変更等は、ふくいのデジタルさんにやっていただいています。
今回のこのチャージの部分もふくいのデジタルさんだっけ?
[DX推進課長]
チャージの分のキャンペーンの原資についても、(1)のABC賞はふくいのデジタルさんの企画、(2)の方のiicaJCBカードの方は福井銀行さんの企画になってございます。
[記者]
こういったデジタル通貨、先行して大手のPayPayなどがもうすでに浸透している中で、PayPayなどでは料金を払った際にポイント還元というような仕組みで、利用者に対してインセンティブが生じています。今回のキャンペーンなどは、まさにそのインセンティブの一環になると思いますが、どうしても既存のインセンティブが大きいので、ふくいのデジタルの「はぴコイン」をいかに広げていくか。この取組みについてはどのようにお考えでしょうか。
[知事]
これは基本的にはシェアの争い、民間同士の競争というところはあると認識をしていますが、先ほど来申し上げてますように、「はぴコイン」というのは県内のいろいろな需要の喚起も一つありますし、それからまた行動変容を経て、社会そのものをこう変えていく。それは公としてプラスの方向に変えていくという、一つの大きなツールだということを認識していまして。なおかつこれだけ大きく県内全域で使える地域通貨、もしくは仕掛けを持っているというのはなかなか全国にも少ないと認識をしていますので、私どもとしてはそうした公共性の部分に着目しながら、これからも「はぴコイン」を十分活用させていただいて、結果として多くのみなさんにこの「はぴコイン」、ふくいのデジタルのこのシステムを使っていただくことにもつながっていくのではないかと認識しています。
[記者]
「はぴコイン」のチャージ機能の部分について、直接は関わりないかもしれませんが、他県の導入事例を見ると、公共料金の引き落としや、納税に使用できる例も見られるかなと思います。なかなか普及していかない部分がある中で、使い勝手を良くしていくことに関して、利用店舗を増やしていくことはもちろんあると思いますが、どこまで流通させるか、どのように活用できるかという部分では知事はどのようにお考えでしょうか。
[知事]
そうしたご議論があるということは十分に認識をしています。私どもとしては、もともと「はぴコイン」の位置づけについては県内の経済の循環にできるだけ使っていこうと、例えば行政が何かお金を投入するにしても、4000円出せば5000円分の商品券ということで、5000円の経済波及があるだろうと。こういうような考え方で活用させていただいているという意味から言うと、もともと税金として払われるお金の部分をそのまま右から左に移すというところにあまり着目していないというところが一つあるので、現状において今こういう状況になっているということです。一方でできるだけ公金について、多様な手段で支払いができるようにしようという大きなお話はあることは認識をしていますので、そういった点についてはまた別の課題としてこれも含めて検討していくということかと思っています。
[記者]
「乗り換えキャンペーン」の部分について、枝葉の部分になるかもしれませんが、このキャンペーンを通じて一定程度、敦賀乗り換えをされている方のデータが収集できるのかなと思いますが、そういったものを活用される可能性はあるのでしょうか。
[新幹線建設推進課長]
「乗り換えキャンペーン」を通じてのデータ収集というのはできません。通信の機械を設置しまして、そこで電波を出して、それをスマホで受信した方に対して、一方的に通知が行く仕組みになっていますので、数字が取れるものではございません。
[知事]
しかし少なくとも当たった人は、ふくアプリをダウンロードすることになりまして、それで住所など何か属性をとるんじゃないの?
[DX推進課長]
ふくアプリは、住所、氏名、年齢、そういったものも全部取ります。
[知事]
ですのである程度、これによって2000人については新たにふくアプリを入れていただくこともあると思いますので、効果はあると思っております。
[記者]
「#7119」の部分について、現状、そこまで都市部に比べて逼迫はしていない状況ということですが、医師の働き方改革という観点で導入を求められる声もあるかなと思いますので、改めて「#7119」を導入される意義について伺えればと思います。
[知事]
これは全くおっしゃるとおりでして、これまでは福井県は大都市部に比べて比較的、救急車の逼迫度合いが大きくなかったということで、コストもかかりますのでそういったところは今までは他に比べて必要性が大きくなかったと。こういうことを申し上げましたが、一方でやはり救急要請も増えてきていますし、また医師、看護師も含めて医療関係者の働き方改革、残業規制の適用も受けるということになってきていますので、効率化を図るということで、今回導入をさせていただくこととしたというところです。
[記者]
「#7119」について、今もおっしゃっていたとおり、都会と比べるとそこまで逼迫度合いは大きくなかったという話でしたが、具体的な数字でどれぐらい、あるいは今年度に入ってどれぐらい逼迫度が増しているということがわかるものがあれば伺えますでしょうか。
[知事]
今数字は持っていないので、また後ほど聞いていただければと思います。
[記者]
この番号にかけると看護師さんなどが出てくるかと思いますが、これはどちらにつながるものになるのでしょうか。
[知事]
東京ともう一箇所はどこかというと、事務局は福岡にあるそうです。しかし事前に福井県の状況をちゃんと研修もして、状況がわかるような形で運用を始めていく。ですのでそういうこともあり、3か月ぐらいまだ期間があるという状況だと聞いています。
[記者]
実際に電話されるのは県外ですが、実施主体はあくまで県だということでしょうか。
[知事]
そうです。ちゃんとその人が住所など言われれば、画面にはその住所が出てきて病院がどのあたりにあることや、いま開いている病院はどこであるなど分かるようになると聞いています。
[記者]
こどもの救急医療電話相談も同じ場所にかかっているという形でしょうか。
[知事]
そうです。
[記者]
北陸新幹線の問題で伺いたいのですが、今回の国の方で小浜ルートの工費が当初の想定の倍、4兆円という試算が明らかになったことを受けて、知事、どのように受け止めているかということと、費用対効果が大きく下がるのではないかと懸念されるのではないかと思いますが、また、これによって米原ルートという声が強まる恐れもあるかと思いますが、その辺をどうとらえているのか、今後の見通しなどを含めて、現在の認識をお願いします。
[知事]
まだ、全く私ども、今報道が出ていることはよく承知をしていますが、3.9兆円という数字であったり、それから、その他についても駅の数が、という報道も拝見しましたが、なんら説明を聞いていませんので、今のところ確たることは存じ上げないというところです。
一方で、報道の内容を拝見して、私として考えたのは、非常に大きくなったなという印象とともに最近の物価の高騰とか、人件費が上がってきている。またいろいろな形で、例えば建設業についても、働き方改革で、時間外の従事の時間、残業時間の制限が完全適用になってきている。こういうことを考えると、これまでも、例えば足羽川ダムもこの数年、三~四年の間に1.9倍ぐらいに上がっている。こういうような状況を踏まえると、そういった影響を受けてきている。平成29年の3月に、前回は、ルートが出されているので、その間の時の経過と最近の物価の高騰の影響を受けているということなのか、と理解をしています。B/Cについても、どんな数字になっているのかということはよくわかっていません。1.1だったから0.5だろうと、こういった話かと報道は見ていますが、これは一般的には物価でコストが上がるということは、Bもそれなりに上がるとは思いますが、相当厳しい状況なのだろうと思っています。ここのところまたよく国の話を聞いてということですが、ただやはり一つ思うのはB/Cのところで、敦賀から大阪までの間だけのB/Cを考えることの合理性も、よく議論をしていただく必要があると思っています。社会的割引率と言われるところも4%のままになっているということでいいのかと。これは長期金利にある程度連動していると思いますが、物価の高さなど、そういうことから言っても4%というのは現状からそれが本当に正しい数字なのかということもあるでしょう。また、道路等の場合は、新たに作る区間ではなく、全線での経済効果、ベネフィット、こういったところもよく見てやっていかれるとも聞いています。合理的に考えないと、明らかにこの北陸新幹線は、敦賀と小浜、京都、大阪とつながることで、国土強靭化を含めて大きな、質的な違いも出てくるので。そして金銭的な面、さらには、他に代え難い国土強靭化の面、こういったことも、十分に検討していく必要があると思います。米原ルートの話というのは、これも平成28年、29年のルート決定の際にも議論されているわけで、その時から物価高騰だとすれば、同じように米原ルートの方も上がってくるというようなことが、一般的にはわかりませんが、上がってくるだろうと。そういう中で、それを超えて、乗り換えなし、そして近くなって早くなる、こういうことの効果で今のルートが決まっているので、しっかりと将来世代の発展のためにも、必要な社会基盤だと思っています。中途半端なことをしないで、ここは腰を落ち着けて議論をした上で、しっかりと一日も早く全線、小浜・京都ルートで大阪につないでいくのが必要だと思います。一つの例で言えば、米原ルートになるともう福井で言えば、乗っている時間が1.4倍になって、料金が1.5倍になることがずっと続くわけです。これは金沢にしても富山にしても20分程度時間が、片道で毎回20分程度伸びた上に、二千数百円、毎回多くのお金を払い続けなければいけない。国家百年の計というものがありますので、私はそういう考え方に立った議論をしっかりとしていただいて、一日も早く、財源の議論も整えていただいて、認可・着工もこちらの方に持っていっていただきたいと考えています。
[記者]
北陸新幹線の県内開業から4か月経ちました。ところどころで知事もおっしゃっているかと思いますが、県内での新幹線の効果も大きいものがあり、その中で4か月経って、改めて問題点も見えてきているところがあると思います。改めてとなりますが、県内への効果と、今課題として県が取り組んでいることについて教えてください
[知事]
北陸新幹線の効果は、比較的順調に、その後も続いていると認識をしています。大きく言いますと、4か月目を経過して、最初の1か月から、1か月ごとの全国からの入り込みの状況から言うと、最初の1か月は38%増、次の1か月は21%、その次が26%で、最後の直近1か月、4か月目は19%増と、大きくは凸凹していますが、1か月単位で見ても効果は続いている。特に、関東圏の伸びは、最初の1か月は63%の伸びでしたが、直近の1か月で見ても、67%ということで逆に伸びています。数からいっても、関西や中京は少し下がってきていると思いますが、これは比較的、手段が変わっていなくて、いつも近しい関係にあるというところですが、関東が67%、それから信越地域は2倍のままずっと変わっていない。こういうことを見ると、やはり知られざる福井へという部分が、継続している。関東は、数の上でも関西の伸びを上回るような状況ですので、根強いなと思っています。そういう意味では、ハピラインをはじめとした他の鉄道やバスなどでも堅調で、バスは平日も含めて、一般利用も含めて全体で1割ぐらいずっと伸びた形になっている。ハピラインも1割増ぐらいをずっと続けてきている状況です。タクシーも、乗っている人数はそれほど変わらないのに、売り上げは24%増えているということで、長距離を乗ってくださる方が増えているというようなこともあります。旅館の方に伺っても、目先も週末はだいぶ混んでいるし、これから夏休み、秋に向けても非常に好調だというようなお話も伺っていますので、新幹線の開業効果というのは、駅前の人出も含めて、続いているかなと思います。しかし濃淡がやはり少しずつ明らかになってきているというのはあると思います。例えば駅前などでも、新しくできた店には、たくさん人が集まっていて、既存の商店街のところで少し苦戦をしているというような話もあります。それから旅館などでも、福井などの新幹線駅から離れていくと効果が見えにくいというような話もありますし、市や町ごとに見れば、例えば勝山市は1.8倍ぐらいのお客さんが増えているということですが、それ以外のところでは100%、昨年と比べて90何%というところも出てきていますので、こういった、新幹線効果が直接行くところとそうでないところをよく見ながら、また次の手立ても考えていく必要があるのかなということです。
[記者]
それを含めて、今後、敦賀以西の大阪まで早期につなげていくことが大切になってくるかと思いますが、先ほどのお話出たように、建設費が上がったりルートの問題が出てきたり、着工が遅れていたりなど、色々問題もあるかと思いますが、知事としては今後も国に訴えていくことは変わらずという認識でよろしいでしょうか。
[知事]
北陸新幹線の建設の効果というのは、今回の福井を含めてとても大きいということが、今回の福井・敦賀開業でも証明されたと思っています。福井はもちろん、移動する人の数も増えているということはありますが、何よりも福井ということを初めて知ったという人を含めてよく知っていただくという、イメージの効果も非常に大きいと思っています。そういうことで、福井の駅前も非常に賑やかになっています。他の駅の周辺もそうですが、お客様だけではなく、県内のみなさんも楽しくて出てくるということも広がっていると認識しています。これはすでに大阪の吉村知事も、まだ開業前でしたが、敦賀に来られた時に、敦賀の周りについて「すごく変わりましたね」と、その上で「早くしないといけませんね」「大阪まで早くつなぎたい」とおっしゃっていましたが、まさにそのとおりで大阪につなぐことで、この北陸新幹線の効果も最大化、しかも大きく上がっていくと思います。今まで東京一人勝ちだったところを、やはり大阪を含めた関西地域がぐっと上がってくることで、日本全体の発展に大きくつながっていく。そして先ほどから申し上げていますが、北陸新幹線ができれば、仮に南海トラフ地震があっても、マイナスの影響を最小限に食い止めることができる。これは、北陸新幹線の小浜・京都ルート以外には考えられない、米原ルートではほとんど大阪に影響はないと思いますし、全国にも影響はほとんどない。なおかつ、地震などが起きた際に、同じように止まっていくことになるので、こういったことを国家百年の計という発想で、色々な課題があると思いますが、乗り越えていただく、そういう整備委員会の議論を期待しています。西田委員長が言われているように、年末には、来年度着工予算を持って詳細ルートを決めて、そして来年度末までの着工を目指すということをぜひ実現していただけるように、我々も沿線全体としても強く後押しをし、活動させていただきたいと思っています。
[記者]
今月、奥越明成高校で教諭による盗撮事件があったかと思います。ここ数年、教師による生徒への猥褻行為などの逮捕事案がとても増えています。主体的な管轄は教育委員会になるとは思いますが、新しく教育長を任命された知事、そして子育てしやすい福井県を目指されている知事としては、安心安全に子育てできる環境を整えていくために、国会では日本版のDBS法案も可決されましたが、きちんと整うまでには数年かかると思います。子どもたちの生活の中で数年というのは大きい時間帯で法案が整うまでに大人になってしまう子どもたちもいるかと思いますが、いま何かすぐ対策を取ることや、県独自で何かやっていこうということなど、知事が考えられていることなどはありますでしょうか。
[知事]
学校というところは、非常に、思春期も含めて子どもたちの多感な時期を、しかもある意味閉ざされているというか安全性が確保された所で自由に物事を考えたり生活したりすることで、子どもの成長というものを促していく場所だという意味では、今回の事案も含めて、過去の事案もそうですが、性的な、色々な暴行、こういったことは言語道断、許されない事態だと考えています。これについても、今回の件もそうですが、藤丸教育長に対してもすぐに、何かが起きるとそのことに対して過去もこうだったという通知を出すということに限らず、とどまらず、抜本的にこうした事態をどのようにして抑えていくのかということについて、至急検討して、また市や町との関係、特に義務教育のところは大きいので、市や町とも十分に連携をとって、二度とこういうことが起きないように、体制を早く組んでいただきたい、対策を考えてほしいというふうには申し上げているところです。抜本的には、一つには外からの話でDBSの法律といったことも言っていただきましたが、そういった社会全体としてもこれをどうやって抑えていくのかといったことについても取り組みを進めていますので、県としてもそういったものにも、できるだけ遅れることがないように、しっかりと、また県独自のことも含めて、検討していっていただく。また必要があれば私どもとしてもそれに協力をしていくことをしていきたいと考えています。
[記者]
体操女子の宮田笙子選手が今回、まだ疑惑の段階ですが、一度チームを離脱した形となってしまって、モナコに行かれる前に知事も宮田選手にお会いした立場もあり、現在どういうふうにこの事態を受け止めていらっしゃるかについて心境とご所見をお願いします。
[知事]
真相のところはまだこれから調査と伺っていますので、その結果を待ちたいとは思っています。しかし事実として、いま事前合宿のところから離脱されているというような状況のように承っていますので、大変残念でありますし、また報道のようなことがあるのかどうかわかりませんが、そういったことがないことを祈るというといけませんが、もしあったとすれば、これは遺憾なことだと思っています。県民としても大変応援をしている選手の一人であります。しっかりと今回のことがどうであったかということも明らかにしていただきながら、また今回離脱ということであれば、次に向けてしっかりとご自身として必要な反省もして謝罪もするということにもなるのかもしれません。これは本当にどういうことかわかりませんが、私はとにかくそうした反省や謝罪はしっかりしながら次の飛躍に向けて、また成長していっていただくということも一方で希望をしているところです。
[記者]
8月9日に関西電力美浜3号機で11人が死傷した事故から今年で20年を迎えますが、この件に関する知事の受け止めを伺います。
[知事]
個人的にも非常に印象深い事故であり、私が赴任したのはまさに20年前の7月2日であって、直後に、先日で20年になりましたが福井豪雨があって、それの対策だったかどうか覚えていませんが、今の庁議室、当時の701会議室で、西川知事もいらっしゃって会議を開いていて、いろいろなことを議論していたときに、午後であったが職員が走ってきて、美浜発電所から白い煙が出ていると、負傷者も出ているようだというような話を聞いたのが第一報でした。非常に衝撃を受けたし、安全性というのがいかに重要か。最初は、本当に原子炉そのものに何かあって起きているのでないかという大きな不安から、もちろん11名の方が亡くなられたり負傷された大きな事故ですが、いろいろなことが頭をよぎったなと思っています。
そういう意味では、この件については、やはり原子力発電は安全が最優先ということをさらにこういう機会ですので、事業者、国もそうですが、しっかりと肝に銘じていただいて、これからの安全な運転に心がけていただきたいと思いますし、私どもとしても、こうした事業者の活動を細心の注意で監視をしていく、こういったことを続けていきたいと考えています。
[記者]
来年になると関西電力の現状運転している7基のうち5基が40年を超える運転に入ることになります。いずれも規制委員会から安全性が確認された状態での運転ではありますが、今後より一層、福井県としても厳しく事業者を監視していく姿勢が問われると思います。常々知事も安全最優先の立場から厳しく事業者を監視していくと発言されていますが、具体的にはどういったかたちで事業者を厳しく監視していく考えか伺います。
[知事]
安全性の確認は日頃からさせていただいているように、最大限、たとえば、長期運転のところが再稼働していくというような時には、職員を現場に張りつけて監視をしていくというところから、日頃からとにかく何か起きた時にはすぐに報告するようにということを、事後的にも遅ければあれが遅かったのでないかということも含めて、しっかりと連携も含めてやらせていただいているところであり、こうしたことを今後ともきちんと続けていくということが大事だと思っています。必要なときには必ず安全専門委員会の意見も聞きながら、国に対して、そして事業者に対しても申入れを行っていくということもさせていただいています。
また一つは、美浜発電所の事故の大きいのは、やはり現場が遠かった。その後、見える場所に現場がなかったということを変えるきっかけにもなったということで、原子力事業本部が美浜に移ってくる。そして機能がこちらの方に、人の数も含めて非常に大きな機能が移ってきている。それから地域の振興ということにも、関西電力本体の目が向くようになった。こういうことも大きかったと思います。多くの従業員の方が福井で生活をして、一緒に子育てをたとえばするということになれば、同じ気持ちで原子力発電所の安全性ということを考えるようになるわけですので、こういった地域の振興ということを通じた意義というものを今後にも生かしていく。そういう意味では、国や事業者に対して、いろいろな地域振興、課題解決を求めていますが、こういったこともしっかりと前に進めることで原子力発電の安全に運転することの大切さということを事業者とも共有していく、こういったこともしていきたいと考えています。
[記者]
昨年10月に関西電力が使用済燃料対策ロードマップの中で一番直近の予定が再処理工場の2024年度上半期のできるだけ早期の竣工ということになりますが、現時点では、先日の規制委員会の会合でも耐震設計の審査が行われているところだという認識だと思いますが、9月までに本当に完成できるのか不透明な状況が続いています。知事の現状の認識を伺いたいです。
[知事]
これについては、先日の規制委員会の会合において、審査対応の全体計画を提示するようにという指示があったと認識しています。その上で、日本原燃の増田社長が、全体のスケジュールとして、竣工目標を変える必要はないという考え方を述べられているというところだと思います。
いずれにしても、目標は9月末までということになるので、ここのところは、審査の内容をしっかり指示を受けて、スケジュール感をしっかり出していただくということだと思いますし、私どもとしても審査の過程の状況なども見ながら、今後必要があれば、国や事業者に対して、いろいろ話を聞くということからはじめていくということかと思っています。
[記者]
今月にも開かれる共創会議で、関西電力から地域振興の考え方、取組みを示したいとのことですが、それに対する知事の期待感を伺います。
[知事]
まさに期待感というか、これまでいろいろな関西電力が次にやりたい、こういうことをやっていくんだということなどについて、国や関西電力に対しても、いろいろな協力もさせていただいている。こういう中で、やはり福井県の原子力行政三原則の中にもありますが、恒久的福祉の実現というところの一つ大きなポイントになるわけであり、それをかたちにするのがこの共創会議であり、そこのスケジュールになると思っているところです。そういう意味では、我々はこれまでも、たとえば原子力防災、避難道路も含めて、これの強化ということも求めているし、いろいろな廃炉措置などで地元企業の参入をもっと拡大すべきだとか、原子力に対する理解をさらに拡大していく、促進していくべきだとか、または地域の課題という意味でも、医療であったり地域交通、こういったものをもっと充実させていくということにコミットすべきだというようなことだったり、企業誘致、移住定住、こういったものもさらに力を入れていく。そして、国に対しても、電源三法交付金などを拡充していくように、こういったことを求めているので、こういったものがこの共創会議の中でしっかりと工程表の中に位置づけられることが必要だろうということで、ワーキンググループも含めて、私どもから強く求めています。また北陸新幹線とか、舞鶴若狭自動車道の4車線化、こういった全国的なプロジェクトについても、省庁横断的に政府全体で対応していくということも求めている。こういったことを具体的なかたちで書き込んでいただきたいと考えているところです。
[記者]
今おっしゃったように、嶺南地域の振興とか課題の解決に向けた取組みというところで、電力事業者や国の取組みが、仮に不十分だと考えられるようなものが出た場合に、審査が続いていますが、県内の乾式貯蔵施設の事前了解にも影響を与えるというのはあり得るのでしょうか。
[知事]
一般論では、なかなか申し上げられないことだと思いますが、大きく何もしないみたいなことを言われれば、いろいろなことを考えなくてはいけないし、事柄というのは程度を見ながらだと思う。すぐに、乾式貯蔵の話に行くとか、何に影響するとかというのは、中身を見てからだろうと、決して否定もしないけれども、中身を見てということだと思っています。
[記者]
新幹線の敦賀以西について、知事は国家百年の計で大きな観点から、建設費が倍になる見通しだが、考えていく必要があるというところですが、これも公共事業の観点からいくと、このB/Cの1倍以上というのは、財務省など、金を出す、国費を出すという側から考えると、おそらく重要な指標だと思います。国に予算付けをするために、B/Cはどのようなことを考えていくべきかというところをまずお聞かせください。
[知事]
まずB/Cのところは、メディアには今回0.5ではないかなど書いてございましたが、まずは国交省が算定すると認識をしています。その中で先ほども申し上げましたが、コストが上がるということは、Bの方も物事の価値が上がっていますので、そういうことから言うと、Bの方もある程度は上がるのではないかということも1つ考えられるということは申し上げました。その上で私はB/Cというのは、道路などを例に引いても、この新しいここの区間だけで物事を考えるというのは、特に今回の北陸新幹線の場合は、あと2割繋げば全体が繋がって最大の効果が発揮できる。そういうこともあるわけですので、やはり全体でものを見ていかなければいけないということも大きいと認識をしています。それで、それらを持って、なおかつ経済効果だけでない国土強靭化、南海トラフ地震が起きた時に東海道新幹線は1か月程度不通になると言われていますが、個人的見解として申し上げれば、南海トラフ地震が起きた時に、通常のようにすぐに直しに行けるかといえば、そこに辿り着くまででも大変な状況になるということは、防災をやっていた関係から言うとそこに辿り着くのも大変だろうというようなことで、しかも広い範囲で、いろいろなところを助けに行かなくてはならない。こういうことから考えるとなかなかそう1か月で行き来ができるようになるというのは、想像は難しいとも思いますが、そうでないにしても、その間毎日20万人、東西行き来ができない、こういったことでそれを半分に減らせる。北陸新幹線があるかないかの効果は、単なる経済効果ではなくて、その先の日本の発展に辿り着けるかどうか。そこでバタッと倒れてしまうかもしれない日本経済を、少しでもなんとか立たせておけるかどうかの大きな瀬戸際だと思いますので、こういったことを、もしもそれがB/Cの中に反映されていないのであれば、十分に政治として、そこのところは考えていただく必要がある。こういうふうに私は思っていますので、次の世代のみなさんの発展のための新幹線だということは、十分に念頭に置いておく必要があると思っています。
[記者]
もう1点、建設費が増額の倍になると、地元負担も相当大きくなると思われますが、これからその着工5条件の財源議論を始めていくと思いますが、地元負担の軽減について、何か国に、政府与党に要望するお考えはあるでしょうか。
[知事]
これは既に、私どもがいろいろな形で国に、政府もしくは与党に対して要請する場合にも、財源議論をしっかりと進めていただくということと共に、地元負担をできるだけ小さくしてほしいということを申し上げています。財源の議論は特に地元負担に関わる部分から言えば、まずは貸付料をいかに極大化できるかということがひとつあるわけでして、それで残った部分を国と地方が2対1でみていく。こういうことになって、地方財源としては2対1になってくるわけですが、その上で交付税措置というのがあって、実質的な地方公共団体の税や交付税で賄う、一般財源で賄う。こういった部分はさらにその2対1の中の交付税措置を除いた部分ということになりますので、そういったいろいろな部分を、貸付料を極大化する。できれば国費なんかもできるだけ追加してもらったり、交付税措置なども充実したりするなど、いろいろな手段があると思います。そういったことを含めて、やはり地域で持てる範囲に収めないと、そこがネックになって、大切な事業でも進まなくなるということになりますので、そこは十分に考えていただきたいと思います。これからやはり大都市部に入ると、大深度の地下のトンネルが増えてくる。そうすると、あの1キロメートルあたりなど、距離あたりの単価も上がってきますので、そうするとやはり大都市部の、整備新幹線は大きく言うと、東京から北陸の方へつなぐという、もちろん先は大阪へということでしたが、今までの流れは地域振興新幹線ではあったわけですね。これからの地域振興新幹線は、その大阪・京都の地域の振興というところだけで考えると、単価が上がっていくというところもよく考えていかないと、本当に全く今までと同じ枠組みということで考え続けるということは、元々質的に転換している新幹線だということを考えないと、実現可能性も低くなっていってしまう。これは確実に実現しなければいけない新幹線だと思うので、そうしたら地元負担についても考えていただきたいと思っていますし、これからも強くお願いをしてまいります。
[記者]
北陸新幹線の敦賀以西の小浜・京都ルートに関して、公費のお話も出ていましたが、一部報道で工期が伸びるかもしれないというお話も出ています。知事は早期着工と新大阪への延伸を訴えておりますが、この点に関して受け止めをお願いいたします。
[知事]
これもあの報道でそういうことが出ていたということであって、我々もまだそういった状況なのかどうかということを聞いていませんので、直接的なコメントはできませんが、一方で、今回北陸新幹線を整備する中で、大深度の地下トンネルをずっとやっていく。非常にこれも工期が長いことになると思いますし、駅の部分が非常にいろいろな調査、特に今回がまだ確度が高くなっていると思われるのは、この2年間、北陸新幹線事業推進調査費で詳細なボーリング調査も必要なところは行われているところで、確実な年数などはおそらく出てくるのだと思います。そういうことから言うと、もしも長くなってくるということがあったとしても、ここのところは先ほど来申し上げている、将来国家百年の計、そういうような中で、しっかりとそれを受け止めながらやっていくということは重要なのではないかなとは思っています。
[記者]
ふるさと納税についてお伺いいたします。総務省は来年の10月から利用者にポイントを付与する事業者を使って自治体が寄付を募ることを禁止するという方針を示しましたが、楽天グループなど一部反対もあります。「ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体連合」の共同代表も務められていますが、ふるさと納税のあり方と、今回の新ルールの適用についてご意見をお聞かせください。
[知事]
ふるさと納税というのはとても大切な制度だと認識をしています。人の循環システムと私たちは言ったりしますが、子どもが福井で生まれて、その子どもが18歳だったり、就職のときだったりで、東京や大阪など大都市圏に出て行く。そしてまた年齢を重ねてきた後、またふるさとに戻ったり、ほかの地方に行って住みたいところに住んだりなど、こういうような人の循環のシステムを考えたときに、大きく人生80年だとして、最初の20年と最後の20年は、税金をあまり納めない。消費税は納めますが、所得課税はほとんど納めない。こういう中で、40年住んでいたところだけに税金が落ちるというのは、やはり人のライフサイクル全体で見た時にはおかしいのではないかと。この歪みを正す1つの手段がふるさと納税だと考えておりますので、これは本当に長く、しっかりと守っていくべき制度だとまず考えています。その上で、もう1個重要なこと、というか、これも元々当然大事なのですが、これは税金であるということだと思います。税金は100%、私どもが早く納めたからといってまけてもらえるものでもありません。逆に言うと、痛税感というか、取られるという意識が強いのですが、ふるさと納税のいいところは、さらにこれを納税、納めるという意識もできるので、そういう意味での良さもあると思います。しかしいずれにしてもこれは納税ですので、税についてはしっかりと認識をして、このお金の行き先は、寄付ですが、税額控除という形を通じて、ぜひ住民税の納税通知書をみなさんご覧いただきたいと思います。5月の末に送られてきていると思います。これを見ていただくと、昨年納めたふるさと納税分引く2000円が、もちろんおよそ住民税額の2割など、上限があるのですが、ちゃんと引かれています。私は毎年確認していますが、きちっと引かれています。そういうことで寄付だけれども、結果として税で穴埋めされているということがとても大事なんだと私は思っています。そういうことからすると、もちろんポイント付与の財源というのが、手数料の中から出ているのかいないのかということについてのご議論もあるようには伺いますが、いずれにしても、手数料収入ということを前提にした商行為でポイントを生み出してやられていると認識をしているところでございます。税金をA地点からB地点に移すとしても、できるだけ多くの税金が納税者の気持ちに沿ってB地域で使われるということが一番重要なんだろうと思いますので、もしもポイントで納税者の方に還元する部分があるのであれば、これは税金ですから本来還元はありませんので、本来のふるさと納税の趣旨の方向で、なんだったら手数料を下げていただくなど、こういうようなことにも使っていただけるとありがたいのではないかと思います。私は今回の国の判断というのは、もう1つあるのは、当然国はそうした関係者に対して十分に説明をしていく、これは国民に対してもそうですが、そういったこともしっかりとしていただきながら、やはりある意味で必要な措置だったのか、これから必要な措置になっていくのか、来年の10月から施行ですので、そうなのかと思っています。私どもが、先ほどおっしゃっていただいた「ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体連合」、この中で一般社団法人ふるさと納税協会、こういう事業者が入られています。こういう方々と昨年、共同宣言を出させていただきましたが、この中でも経費削減や健全な発展を目指した活動に取り組む、こういう旨で一緒にやっていただいている事業者からは、一緒に参加をしていただいているというところですので、やはりふるさと納税といういい制度をできるだけしっかりと長く、継続可能な状況にしていくことは大事なのではないかと思っています。
[記者]
新ルールの適用は来年10月ともう少し先ですが、ポイント付与のある仲介サイトを使えなくなることによる県や県内市町のふるさと納税額の影響はどのように見られているでしょうか?
[知事]
これは事業者間、みな同じルールになりますので、ポイントがもらえたから納税していたという人が納税しなくなるということはあり得ると思います。そういった影響はあるかもしれませんが、ただ、どちらかというとみなさんは事業者を選ぶときにポイントは多分考えていたと思いますが、そうでなくて、どこそこを応援したいなど、私はずっと返礼品なしでふるさと納税をいろいろなところにさせていただいていますが、私は全く気にもしないというか、ありませんし、またそこの地域を応援したい、もしくはこの返礼品というか、そこの特産物に魅力を感じて、そこを応援しようという方もいるわけですので、そういったことの動機の方がずっと大きいのかなとは思いますので、できるだけ影響がないことを祈りつつ、健全な発展という意味で、今後のことを考えるとやむを得ない今回の措置かと思っているというところです。
[記者]
今月末から来月頭で全国知事会が開かれる予定で、議題は様々上がっておりますが、福井県として知事として特に重視していることと、訴えていきたいことをお願いします。
[知事]
今回、北陸新幹線が開業したというところで、今年誘致しましたが、まさに北陸新幹線の効果をみなさんに感じていただきたいと思っています。今のところ、ほとんどの知事さんがおいでいただけると伺っていますので大変嬉しく思っています。そしてこの効果を一日も早くやはり小浜・京都ルートで大阪につなぐことということに結びつけていきたい、もしくは頭の中でわかっていただけるように説明をしていきたいということがまず一つ大きな今回の北陸新幹線開業後の全国知事会議の開催の意味だと私は認識をしています。その上で、これから能登半島地震からの復旧復興に向けてこれからの協力関係どうするのか、人口減対策、地球温暖化などいろいろな課題が山積をしていますので、こういったことについての議論もしっかりと進めていく。そしてできればそうした北陸新幹線も含めた整備新幹線の整備促進や人口減対策について、高校から大学への進学、そして就業を見直していく、国としてそういったものをしっかりと構造改革を行っていくべきだと福井県は強く申し上げていますので、こういったことを含めて今申し上げて、いろいろな点も含めて福井宣言というようなものの形にして、まとめていければということで、提案も今全国知事会とさせていただいているところです。そういったことも含めて全国の知事といろいろな形で話し合った内容を政府与党に提言をしていけるようにしていきたいと思いますし、また全国知事会が会議を主催しますが、地元の県としてしっかりとサポートをさせていただいて、実りの多い会議にしたいと考えています。県内も恐竜博物館や一乗谷、永平寺を見ていただくなど、我々が手塩にかけて育てた観光地も、こんなに良くなったというのを見ていただいたり、福井駅前の恐竜を見ていただくのも楽しみにしています。
[記者]
補助金の問題について、水産庁との協議を進めていると承知をしていますが、現在進捗とはどのようになっていますでしょうか。
[知事]
水産庁の国庫補助の歳入の不足、手続きの不備についてご迷惑をおかけしていることに心からお詫び申し上げます。水産庁に対しましては、農水省の最高幹部にもまた財務省にも参りましてお願いもしていますし、水産庁の最高幹部にも、副知事もはじめお願いをさせていただいているところです。今のところはやはり難しいというような状況と認識をしていますが、ただ今回の件について、交付決定はいただいているという状況もありますし、また全国で過去にもいくつかこういった例というのはあることも承知していますので、粘り強く今後ともしっかりとお願いをし続けていきたいと考えていますし、また再発防止策についてもしっかりとこれから9月議会目途ということですが取りまとめをしていきたいと考えているところです。
[記者]
議会の中では隠蔽という言葉を使われて、交付金について言えばですが、その点について、改めてどういうふうになぜ遅れたかというところを教えていただけますか。
[知事]
今回の4.6億円が隠蔽ということには当たらないのではないかと私は思っています。これはお金をいただけないかということのどうやって4.6億円をいただけるのかということをすぐにやりながら、一番近い議会で最初からご説明させていただいています。3億円のお話については、これを隠蔽と言われるようなお話も伺ったことはありますが、これについても当時はとにかく取り返そうということを担当部局中心に一生懸命やっていて、結果的に私も含めて、深く反省をしていますが、結果として公表はできていなかったということについては、深く反省をしているというところです。思いが至らなかったということに深く反省しています。
[記者]
ライドシェアが7月下旬ぐらいからという話があったかと思うのですが、現状はどういう状況でしょうか。
[知事]
ライドシェアはまだなかったと認識していますが、まもなくだとは聞いていますので、数日の話がわかっていませんので申し訳ありませんが、特に遅れているということはないと認識しています。
[記者]
それに関連して、事業者のことは就業規則の見直しであるとか、若干の負担が増えるというところもお伺いしているのですが、そのあたりについてはどういうふうにお考えでしょうか。
[知事]
これはタクシー会社の方で雇われた形で、自家用車を使いながら、もしくはタクシーを使いながらなど、そういうやり方をされるというのが今回の日本版ライドシェアのやり方ですので、今おっしゃったような負担というものが出てきますし、一方で言うと、それが一番乗られる方にとっても安心安全につながっていくことだと認識をしていますので、そこはきちっとやっていただくんだろうと思っています。一方で、今後の議論の展開として、そこからさらに発展していくかどうかは、今後国交省で議論もされると伺っています。それは状況推移を見ていきたいと考えています。
[記者]
宮田選手の関係で、県では駅にサイネージを使った応援のパネルを出していますが、あれについての扱いというのは何か分かりましたら教えてください。
[知事]
可及的速やかに、結果を見てないのでタイミングまで今すぐ確認していませんが、適切な形にしていくんだろうと考えています。
[記者]
適切な形とはどういうことですか。
[知事]
普通に考えると、宮田選手、まだ結果出てませんのでわからないのですが、違和感のないようにしていくんだろうと思います。普通で言うと1人外すということもあるでしょうし、それは今、どこまで決めているかはまだ聞いていませんが、おっしゃられる主旨なんかも踏まえて色々考えていきたいと思います。
[記者]
6月の県議会で出た特定利用港湾についてお伺いしたいのですが、特定利用港湾というのは民生利用をうたった制度であるということは承知しているのですが、昨日も抗議の方が県に来られてました。県として、例えばメリットデメリットをもちろん検討されたと思うんですが、そういう検討状況や、議論があって今受け入れという方向に進んでいると思うのですが、どういう考えや議論があったのでしょうか。
[知事]
特定利用港湾については、今おっしゃっていただいた通り、港湾法に基づいて民生利用として、民生利用の邪魔をしない形の中の一つとして、自衛隊と海上保安庁、ここが船舶を入れて避難の訓練をする、それからいろいろな物資を出したり入れたりする、機械設備などを動かすなど、そういうような訓練について、一回一回手続きを一からやっていくのか、事前から大きな流れを決めておいて、スムーズに進むようにするのかというような主旨において、スムーズに物事が、そういった訓練ができるようにというような趣旨で、今回で指定をされていくことを県としてどう考えるかというような状況にあると認識をしています。これについては議会でも申し上げましたが、一つには大きな災害が起きた時、能登半島地震でもそうでしたが、お風呂を敦賀港にあげて運ぶなど、こういうようなことが、事前から訓練されていれば、住民の避難にも非常に便利にもなりますので、そういったことの効果ということも考えていますし、また反射効果として、港湾の整備が、今岸壁の延伸も含めて、いろいろと事業を動かしている最中ですので、こういったことにも国としても優先的に取り組んでいただけると伺っています。こういったメリットも最大限活用して進めていきたいと思っているところです。安全面、どうやって地域の安全を確保するかといった部分については、これは別途、我々としては原子力発電の立地地域の安全維持のための基地の整備やいろいろな部隊の展開の話などもお願いをしていますので、これはこれとしてしっかりと今後とも続けていくと思っています。
[記者]
関連して、敦賀に置く意義をどう考えているのか、お伺いしたいです。先ほどおっしゃっていたように、敦賀の嶺南の地域は原発もあります。全国的に見ても本州で日本海側に置くのは、敦賀が決まればですが、初めてになる可能性があるということで、敦賀に置く意義について、知事はどのようにお考えでしょうか。
[知事]
これは国の方が指定してきて、こちらというお話がありますので、我々が先ほども申し上げましたが、原子力立地地域の安全性確保のために基地を求めたり、部隊の配備を求めたりということも踏まえて、敦賀港というのは日本海側を見た時に、いろいろな物の移動や人の移動という部分で見ても、重要な港湾、場所だということで、大きな二つの点で国として、特定利用港湾の候補に挙げていらっしゃるのではないかと思いますが、最終的にも国がどう考えているのかということかと思っています。
[記者]
小学校のプールについて伺います。7月の頭に高知市で、小学校のプールが老朽化していて、中学校のプールで授業をしていたところ、溺れて児童が亡くなるという事案がありました。いよいよ夏休みで、プールの利用もあると思いますが、この事案を受けて、県としての対応であったり、老朽化したプールというのは福井県内も多いとは思いますが、それについて、現時点でどのような対応をお考えですか。
[知事]
教育委員会がどういう対応をされていくのか存じ上げていませんので、教育委員会に聞いていただきたいと思います。私も子どもの頃、小学校と中学校が一個のプールを使っていまして、深いところと浅いところを簡易に分けてやっている時に生活したこともありますけれども、やはり安全性第一だと思いますので、こういった事案があれば、しっかりと点検もしていただいた上で、子どもの安全第一に授業もしくは夏休みなんかの開放を行っていただけるように、教育庁の方に注意喚起をしっかりとしていきたいと思います。
[記者]
都知事選のことに関して、お伺いします。知事は従来、東京の一極集中を何とかしていこうとずっと訴えられていると思いますが、今回の都知事選で候補の石丸さんは当初それを訴えられたと思いますが、全体を通してその議論が深まったか、その認識はいかがでしょうか。
[知事]
東京一極集中というのは、私どもから言うと全国的な課題だと認識をしていまして、これはまさに東京都もぜひ認識をしていただきたい。東京都に人が集まっているのが福井から行った人、秋田から行っている人。こういう人たちが東京都を作っているといったところはぜひ認識をいただきたいということですが、一方で私どもが申しているのは国として構造改革をしっかり考えていただきたい。そしてその議論が東京都で行われるということそのものは、私は歓迎をするところです。東京都も合計特殊出生率が0.99ということで史上最低、1.46の福井県と比べればかなり低くなっている。こういったことも十分認識をされて子育て支援もお考えになるのだと思います。合わせてこれを東京都に考えてくださいと言ってどこまでできるかというのはありますが、国として構造を変えていくということの議論に結びついていっていただけるのであれば、今回の東京都知事選挙の効果もあったのかなとも思っていますし、そういったことをこれからも訴えていきたいと思っています。
[記者]
特定利用港湾について関連で、現在、県の方で港湾利用関係者の方々に説明をされているということを承知していますが、一般の住民や県民など、そういった方々への説明の必要性について、知事はどのように認識されているか教えてください。
[知事]
国も含めてこの必要性については、みなさんのお話を伺いながら進めていくんだろうと思っています。いま必要な形でみなさま方にもお話をさせていただいているという認識ですし、必要があれば、どこまでどうしようとしているかのところまでは聞いていませんが、市にもしっかりと声をかけてやらせていただいていますので、地元の理解をしっかり得ながらやっていくんだろうと思っています。
[記者]
現時点では例えば、国に対して住民を対象にした説明会を開いてほしいなど、そういった要望をされるおつもりはないでしょうか。
[知事]
今はまだしていないのかもしれませんが、またよく実態を見て考えていきます。
[記者]
補助金の不備に関して質問をさせていただきたいです。確か過去の事例についても類似の事例がないか調査をされるということをおっしゃっていたかと思います。現時点でどういう進捗なのか教えていただけますでしょうか。
[知事]
これは決算で、決算は客観的に見えますので、決算書で一番最後のものなので2月補正が基本になりますが、2月補正後の予算額と実際に受け入れた決算額、これを引き算して乖離があるとなにか理由が必要なわけです。理由がなければおかしいわけで、この時に理由を決算が違っているものについて、どうしてそうなったのかというので、例えばよく考えられるのは国の交付決定額はもともと小さかったということや、翌年度に財源も含めて繰り越すことなど、理由がもうはっきりしているもの、当然制度的に認められているものがある。そういったいくつかの制度的に認められているものを排除していって、残ったものが事務ミスということになるわけです。こうした決算書類を全部並べて、客観的に数字を出して、一個一個潰すという作業をしているというところです。だいたい年間で国庫補助を受けて行う事業が1000件ぐらいはあるそうですので、いま書類が残ってるのは5年分ありますので、5000件。こういったものを今しっかり調べているというところです。
[記者]
ちなみに現時点では類似の事案というのは今のところ出てきていないですか?
[知事]
いま調査をしている最中で、私のところにそういったことがあったという報告はありません。
[記者]
沖縄で、在日米兵の性的暴行の問題で、自治体への情報共有がなされていないということで問題があって、沖縄以外にも青森や山口でも同様の情報共有がないということがあったというふうに報じられています。福井県内には米軍の基地はないと承知していますが、だからこそ万が一県内でそういった事案があった時の情報共有体制について、何かルールがありますか。
[知事]
県内で、米兵の方が通りすがりに何かするなどということかもしれませんが、今、福井県で、日米協定や日本の刑法とかこういったもの以外で、何か特に持っているというわけではないというとこではあります。ただ、こうしたことは本当に言語道断で、人として、国を超えてあってはいけないことですし、もともと安全を守るために、それはお互いのですけれども、アメリカも日本も安全を守るために駐留しているわけですので、そういったことの安全性、もしくは信頼関係を壊すような行為は絶対に許されないと認識していますので、これについては、沖縄なり他の基地所在の県といったところを中心として、しっかりと情報共有できるような、そういう体制にするように、国は、断固たる措置をアメリカに求めていく。こういうことが重要だろうと思っています。
[記者]
現状で、過去にそういった事案が県内であったということを把握していることは特にないでしょうか。
[知事]
そこは実務的にも聞いていただいた方がいいと思います。私は聞いたことはございません。
―― 了 ――
関連ファイルダウンロード
 20240719資料(ふくいはぴコインの常時チャージについて)(PDF形式 554キロバイト)
20240719資料(ふくいはぴコインの常時チャージについて)(PDF形式 554キロバイト) 20240719資料(救急医療電話相談事業(#7119導入、#8000拡充)について)(PDF形式 206キロバイト)
20240719資料(救急医療電話相談事業(#7119導入、#8000拡充)について)(PDF形式 206キロバイト)
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kouhoukoucho@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
知事公室広報広聴課
電話番号:0776-20-0220 | ファックス:0776-20-0621 | メール:kouhoukoucho@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)









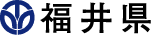


 ダウンロードはこちら
ダウンロードはこちら