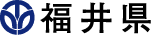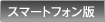職場のトラブルQ&A ~出来高払制の保障給~
問
当社では、営業社員の給与を出来高払制に移行することを検討しています。この場合、全く売上げがない月にも、給与を支払わなければいけないのでしょうか。
答
出来高払制をとる場合には、「労働時間に応じ一定額の賃金を保障」することを労働基準法では義務付けています。これは、労働者が就業したにもかかわらず、客不足や原料不足、あるいは機械の故障など労働者の責に帰すことができない理由によって仕事量が減少し、そのため賃金が著しく低下するのを防止するためのものです。
労働基準法では保障給の額についての規定はありませんが、休業手当について、平均賃金の6割以上の支払を要求していることからすれば、労働者が現実に就業している場合には、平均賃金の6割程度がひとつの目安と考えられます。
なお、保障給の内容については、就業規則や労働契約等で明らかにされる必要があります。
また、出来高払制の賃金でも、最低賃金法に基づいて都道府県ごとに定められた地域別最低賃金(産業別最低賃金が定められている場合は、産業別最低賃金)を下回ることはできません。
解説
出来高払制の賃金は、
- 仕事の単位量に対する賃金を不当に低く定めて、労働者を過酷な重労働に追いやる。
- 一定量の仕事につき、その一部に不出来があった場合に、その全部を未完成として、これに対する賃金を支払わず、労働者の生活を困窮に陥れる。
など、多くの弊害がみられました。
そこで、労働基準法第27条は、労働者の最低水準の生活を保障すべく、労働した時間に応じて一定額の賃金保障を使用者に義務づけています。
また、本条の保障給は、労働時間1時間につきいくらと定める時間給であることを原則としています。
労働者の実労働時間の長短と関係なく単に1か月について一定額を保障するものは、本条のいう保障給ではありません。
本条は、使用者に対し、就業規則や労働契約等において保障給を定める義務を課しています。
ただし、労働契約に保障給の定めが明確にはなされていなくても、現実に本条の趣旨に合致するような給与体系が確立されており、適正に運用されていると認められるのであれば、当該労働契約が無効であるとはいえないとされています。
これとは別に、労働者が就業しなかった場合には、それが自らの都合によるものであるか、使用者の責によるものであるかを問わず、この保障給を支払う必要はありません。
なお、出来高払制で使用する労働者について、労働時間に応じ一定額の賃金を保障しない使用者は、30万円以下の罰金に処せられます。(労働基準法第120条第1号)
参考
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、roui@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
労働委員会事務局
電話番号:0776-20-0597 | ファックス:0776-20-0599 | メール:roui@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)