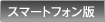知事記者会見の概要(令和7年3月18日(火))
令和7年3月18日(火曜日)
10:30~12:15
県庁 特別会議室

[知事]〔配付資料:令和7年度組織改正・人事異動について〕
組織の改正と人事の異動についてお話をさせていただきます。
4月1日付で人事の異動と組織の改正を行います。主なポイントといたしましては、観光の誘客の促進ということと、そして県内定着、そして医療・福祉、こういった面についても力を入れていく。そして個別最適な学び、教育ですね。それと社会インフラ整備。主に言えば北陸新幹線が開業して1年経過をいたしまして、そこで出てきた課題もあります。また日頃から医療・福祉関係、そして教育の関係、こういったことは非常に重要なポイントですので、そういった点について力を入れて、組織の方でも充実をさせていこうということです。
まず観光の関係で言いますと、課題となっていますインバウンドの体制の強化ということでして、インバウンド交流課を新設してまいります。また、観光プロモーションの関係では、新幹線開業課を廃止しまして、誘客推進課と観光政策課、こちらの方に組織をガラガラと変えていこうということです。プロモーションなどは引き続き誘客推進課でやっていく。また、ホテルの誘致などは観光政策課の方でやっていこうと考えています。また、嶺南地域の観光について、テコ入れが必要だというようなお話もありますので、今まで若狭湾観光連盟、若観連については交流文化部の方でいろいろと対応していましたが、嶺南振興局の方に対応を移しまして、増員を図りながらやっていこうということです。
そして、次に県内定着を図っていくということで、定住交流課を未来創造部の方に移したいと考えています。人の交流というような関係で交流文化部ができたときに、定住交流課を交流文化部の方に移しましたが、最近の県の傾向といたしましては、今回、人口戦略を未来創造部の方の実行プランの中にも入れ込みまして、力を入れていますし、また定住促進の方と繋がりが深いのが、地元就職であったり、U・Iターンの促進であったり、そして女性活躍、結婚応援ぐらいまでが若い方の、福井においでいただいて、Uターンであれ、Iターンであれ、力を入れていく政策ということですので、これらを一元的に未来創造部でやっていくということの方が効率性が高いだろうと。この結婚応援のところまで未来創造部の方でやった後、今度は子育て支援、もしくは妊娠、出産、子育て、巣立ちまでの政策は健康福祉部を中心にやっていくと、こういうことを役割分担にしていきたいということです。また、「ふく育県推進チーム」というものも作らせていただきます。一応子どもの、2人目のお子さんから幼児教育もしくは保育の無償化というのを今年度完全に所得制限を撤廃して実施をさせていただきました。そして高校についても、2人目のお子さんがいる場合は、1人目から所得制限なしで無償化するというようなことで、量的な子育て支援というのはかなり充実をしていると。最終的に国の方が、高校の授業料の無償化は全面的に引き取るということではございますが、そういった方向に進んできているということで、さらに今度はお子さん、もしくはお子さんを持つ家庭、こういったものを中心にしながら、よりきめ細かく。例えば、ふく育さん、こういったことでお子さんを中心に子どもをどう守るかというようなことも考えてきています。ふく育タクシーもありますが、いろいろな制度がありますので、こういったものを一元的に守られる側、そちらの方から見ていいような制度に、全体の調整をしていく、そういうような意味で、ふく育県推進チームということを掲げさせていただいて、副知事をトップとして進めていきたいということで、ふく育県のステージアップを図っていくということです。
またその中の考え方を、軌を一にしておりますが、こども未来課の職員を増員していく。また、こども応援サポーターと言いまして、こども応援ディレクターと、武原さんといって一生懸命頑張っておりますが、こういったディレクターがいろいろなところで、例えば子ども応援していますと、障がいを抱えていらっしゃるお子さんがいる、学校に不登校でなかなか学校に行けないなど、いろいろな環境に置かれている、境遇に置かれているお子さんがいると思います。そういう子どもたちの、当事者で、もしくはそういったことをサポートする組織の中心人物などを一緒になってサポーターに任命をいたしまして、それで子どもたちを官民共創で応援していこうということを考えているところです。
そして、健康福祉部長に初めて医師を登用させていただいて、医療と福祉の融合、これをさらに進めていきたいと考えています。また今も、申し上げましたが、誰一人も取り残されないという考え方にも通じると思いますが、障がい福祉課の関係でも、地域生活支援室というのを置かせていただきまして、例えば医療的ケアが必要な方、こういったさまざまな障がいを抱えている方がいらっしゃいますので、その方、もしくはご家族、そういった方々が全体として地域で安心して暮らせるような、そういう観点から地域生活支援室というのを作っていきたいと思っています。
これも、子どもを中心にしていこうという考え方も同じですが、教育DXの推進をさらに進めていこうと考えています。元々、デジタルタブレット、全国でもトップに全県に配布をしてきましたが、そういうことをさらに学び、学校現場に参りますと非常にタブレットも使われるようになって、それでいろいろな、例えば学校、クラスの中でいろいろな議論をした時の集約にそれを使ったり、デジタル教科書も出てきたりなどしています。さらに、デジタルの教材、もしくはデジタルを活用することの可能性というのは、教育そのものを個別最適にしていく。子どもたちの進度に合わせた教材が選べるなど、こういった可能性もあるわけです。こういったことを今まで教育DX推進室、いくつかの部署に、小学校、中学校、高校など、いろいろな形で分かれていたものを1か所でそれをまとめて、デジタル教材の活用などの学びの変革を進めていこうということと、またチームを作ってここの推進室が進めるだけではなくて、それぞれの部署のところと連携を図りながら進めていくということを考えていきたいと思っています。
そして、教職の魅力発信ということで、人財発掘ディレクターというものが知事部局にいますが、教育委員会にも教職の魅力発信ディレクターというものを置きまして、先生はとてもやりがいがある仕事である、または他のところで働いていらっしゃる、いわゆるペーパーティーチャーのような方々に、今の学校現場はとてもやりがいがあるというようなことを、先生の側からこうだと言うと、ある意味押し付けというか、気持ちが出てしまいますので、そういう先生が魅力的よねということを、先生ではない側から見て、みなさんに中間的な気持ちで発信できる、こういうような体制を作っていきたいと思っています。
また、安心して暮らしていただける社会インフラの整備ということで、県土の強靭化を図っていこうと。能登半島地震が起きて、例えば、上水道の浄水場や、下水道の排水処理場。こういったようなところが傷んだり、途中の例えば大きな病院のようなところの重要な施設、こういったところの配管が壊れたりということがございました。そういったところの耐震化は、福井県内が全国平均よりも遅れているという状況もございますので、今回この上下水道室を新設しまして、こういったことを急いで整備をしていきたいということです。またドローン活用ディレクター、これは能登半島地震の後、また9月22日に能登半島で奥能登豪雨がございました。このときに、すぐに私ども、ドローンでいろいろな情報を集めるということをやらせていただいていましたので、職員を珠洲市に派遣をしまして、上空から写真を撮ることで、土がどの辺りにどれだけたまっているかということも、もう一目でわかるわけです。とてもその後の対応が早くなる。こういうことも分かってまいりましたので、ドローンの活用をさらに先端的に、先進的に進めていける、その方向に進めるために、活用ディレクターを置こうということです。また県有施設の長寿命を図る、財源の確保も重要ですが、どんな形で進めていくのか。こういったことを考える上で、施設長寿命化グループも新設してまいります。
ディレクターもあと2名また増やしてまいります。また動きやすいようにということで、もともと課にいまして、部に上げましたが、これからは私の直轄、知事公室付けということで、私が指示をして自由に動き回れるように、もちろん今まで通りチーム員もつけてグループで、チームで活動ができるようにしていく、こういう体制を強化していきます。また県庁ディレクター応援プロデューサーというもの、寺井くんがチャレンジ応援ディレクターをやっていますが、彼は5年目になります。現状においてもほかのディレクターのみなさんにいろいろなアドバイスをしたり、相談を受けたりしていますので、プロデューサーとして、全体の統括といっても何も指示を出すわけではありませんが、うまく円滑に仕事が進むように、彼をプロデューサーにしていくということです。
そして、職種を超えたキャリア形成応援ということで、今まで特に、例えば土木職の職員というのは、採用しようとしてもなかなかできない、こういう現状にございます。一方で、市町も同じ状況にありますので、県に対して求められているのは、県庁職員としての土木職員だけではなくて、市町に派遣する職員、また今回の能登半島地震でも典型的ですが、今でも14名県から中長期派遣しています。こういった方々の需要はどんどん増えているということで、背に腹は変えられない、もしくは職員の中にもやってみたいという職員がいますので、事務職を土木職に移す。そして林学職に移す。こういった取り組みを始めていきたいと思っています。公務員人生は30年余りありますので、十分にやる気を持って取り組んでいただければ、資格を含めて活躍ができる場もあるのではないかということで、チャレンジをしてみようということです。
そして外部人材の積極登用ということで、最近、地域おこし協力隊をずっと県は増やしてまいりました。とてもよく、みなさんやはりやりたいと言って手を挙げてきていただいている方ですので、非常によく動いていただいています。なおかつ、地域おこし協力隊員という方々は、だいたい3分の2の方は、県内に定着をしてくださるという、そういった状況もございます。そういうことで、国の方の地方交付税制度で非常に活動費も含めて手厚い支援もありますので、20名を33名に、県としては増やしていきたいということで、全国トップクラスにこうやって踊り出てくるという状況になるかなと思っているところです。
続きまして、女性活躍ということで、女性管理職の登用につきましては、今年度、23.2%までまいりましたが、それを25.3%に引き上げるということをやらせていただきます。私が知事になったときは12.2%でしたので、まあ7年かけて倍増以上になったと、こういうことです。現実には、病院も入れますと女性職員は45%ぐらいいますし、病院を除いて、看護師を除いても、32~33%職員がおりますので、まだまだというところはありますが、全国的に見ても、令和6年度の段階で全国2位でしたので、これからも、こうした適材適所ということではありますが、女性活躍の幅を広げていこうと考えています。
そして、管理職登用だけではなくて、その前の段階が非常に重要だ、経験が重要だということは前から申し上げています。そういうことで課長補佐、グループリーダーにも女性の登用を増やしまして、人数も率も、過去最高に引き上げていくということで、次なる管理職候補を育てていこうとしているところですし、職種も、林学職で初めて女性課長を登用するということですし、DX部門に女性職員も積極的に登用していくということも行わせていただきます。そのほか、グループリーダーの特に若い方々が身をもって経験しているような職種のところに若いグループリーダーなどを登用していく、30代のグループリーダーを登用していくことにも力を入れさせていただいています。
またチャレンジ制度ですね。意欲を高めるということで、チャレンジ制度は、庁内公募と、もう1つ、庁内FA制度というのがありまして、少し分かりにくいですが、FA制度の方は、誰に言われることもなく、自分が手を挙げて、ここに行きたいと言って人事課に提案をしてくる。それで、相手方の課と面接をして、いいよということになれば動く。庁内公募はここにやる気のある人、こんなことやりたい人いませんか?と公募をかけて、そこにチャレンジして、募集に通るということで、積極的なチャレンジ制度を活用している職員は80%が希望通り異動ができているということ。そして、特にそういうことはなくて、希望調書にここに移りたいと書いてある、こういうような方々もできるだけ配慮をいたしまして、35.6%ということで、最近統計を取っているだけですが、かなり、だんだん上がってきているということです。
そして働き方改革も今、福井県庁で進めさせていただいています。今まで官民共創エコシステムということを私は申し上げていますが、官民共創ということ、もしくは庁内でも兼業をしていく。こういったことを進めていきたいということで、まず1つは、県庁内の庁内兼業ということで、県庁○○部というようなものを作っていこうと考えています。例えば、デザイン部であったりとか、アナウンス部であったりとか、さらには通訳部など、いろいろ、自分の今の目の前の仕事とは直接関係ないが、結構私得意なのよねと、結構才能のある職員がたくさんいますので、非常に期待をしていますが、そういうものが庁内兼業、もしくは庁内でいろんな議論などをするときの課題解決なんかにも力を発揮していただけるように、日頃から活動していてもらう。こういう○○部っていうのを作っていこうと。もう1つ、今度は県庁外で、兼業をぜひ受け入れたいという企業。もちろんいわゆる本当の利益誘導だけのためにということではなくて、やはり公共性という、公という、例えば、実際にやらせていただこうとしていますのが、バスの運転士、路線バスの運転士のように、公共性があるなというようなものについて、企業から手を挙げていただいて、県庁職員向けの官民共創ポータルサイトを作りまして、職員向けにこんなことやってみない、それで兼業で社会貢献を積極的に支援してもらうと。こういうような仕組みも今回作らせていたただこうと思っています。
また、フリーアドレスということをやっていますが、さらに県庁の中で、市町、民間事業者のみなさんと自由にいろいろな話ができるようなコワーキングスペース、こういったものを作っていく。Fukui Innovation Knowledge Areaという名前、なぜこういうふうにしたかというと、よくフィーカと言っていますが、コーヒーを飲みながら、気楽なお話をしながら、新しい創造的なことをやっていこうということで、fika(フィーカ)ベースというのを作らせていただこうと思っていまして、まずはあの8階にそういった場所を4月から作りますし、あと2か所、来年度内には作っていこうということで、所属を超え、さらには官民の共創ということで、新しい創意工夫を生み出す場所にしていきたい。市町の職員のみなさんがここへ来てテレワークしていただいてもいいと思いますので、そういったこともやっていきたいし、県庁の中の職員が課を越えて、こういうところで仕事をちょっと気分転換にやれば、部を超えた形でのフリーアドレスが実現するわけですので、こういったこともやっていきたいということです。またフリーアドレスもやってきましたが、ついに令和7年度中に本庁内の全職場がフリーアドレス化をいたします。今年度内にも9割近くまで上がってくるということで、非常に評判がいい状況です。そして、テレワークとペーパーレス化も順次進めてまいりましてテレワークは月1回以上行う職員は昨年度37%でしたが、53.1%まで上がってまいりました。またペーパーレス化も63.5%まで来たということです。そういうことで、フリーアドレスは出先機関にも拡大をしていきたいと思いますし、庁内でも、フリーアドレスで課の定員の分だけ席がない、要は100%通勤してくると席はありませんよという課は、現状4割ぐらいになってきています。こういったことも進めながら、庁内でもっといろいろなところで仕事ができる。市町の庁舎へ行って仕事をしてもらってもいいし、公共施設などでテレワークしてもらってもいいし、またワーケーションで自分が遊びに行ったところで仕事をするもいい。そういうことで、職場イコール県庁という発想を早く、自分がいる場所が職場なんだという方に変えていただきたいということを推進させていただきますし、そのためにフレックスタイム制、選択的週休3日制を全職員に拡大をさせていただきまして、ハイブリッドワーク、庁内で仕事する時間があって、外で仕事する時間があって、全体で1日分の仕事をする。もしくは1週間分の仕事をする。こういったことを全国トップクラスに、全庁的に来年度でフリーアドレスになるというのは、東京都、奈良県と福井県だそうで、福井県が、全体として見れば、全国トップクラスの働き方改革が、次のステージに進んでいくと考えているところです。
そして、安心して育休が取れるということで。男性育休については、令和6年度中も、100%達成できそうということですし、また、1か月以上の育休の取得は88.8%ということで、国が目標としています、来年度中で1週間以上の取得率85%を1年前倒しして、県庁としては達成ができるということです。また、男性育休も平均取得日数は、これは年末までですが66.4日ということで、順次こう広がってきて、もう2か月を超えてきています。育休を取得する時には、手当が、少し給料が減りますので、大体年次有給休暇と合わせて使います。日数で言いますと、79.5日になっていますので、もう80日、みなさん、男性も普通に取るような状況になっているということです。女性も含めた育休代替要因の確保も行ってまいります。
異動の規模ですが、平均より少し多い感じです。特に多いというわけでもありませんが、今年の異動はこういう数字になっています。また若手の登用もさせていただいているところです。また、首都圏統括監を置きまして、未来創造部に置きますが、東京事務所などでイベントを行ったりするのがバラバラにならないように、統括をしていこうということです。そして原子力リサイクルビジネス、夏にも立ち上げということがございますので、嶺南Eコースト計画室に増員を行います。また、8月11日に山の日全国大会を開催しますので、その準備も行ってまいります。そして林業の方は、Fukui Forest Designという、大きな林業と小さな林業をまとめる副部長を置きます。福井縦貫線というのは、フェニックス通りを南に行くと、途中で4車線が3車線になると思いますが、あのところをいよいよ用地買収が始まりますので、体制の強化を行ってまいります。国費の関係でも課題がありましたので、それの強化を行いますし、県立若杉中学校の開設の準備も行ってまいります。
~質疑~
[記者]
17ページの人事異動の規模なのですが、総数が1,038人ということで、これは平成27年度以降の10年間で何番目に多くなるような規模になりますか。
[人事課長]
過去10年間で行くと2番目になります。
[記者]
最多の令和元年度に続いて2番目ということですか?
[知事]
大きくは違っていませんがそうですね。
[記者]
今回の異動について、観光というのが一つの目玉になっています。観光の強化ですね。その点を伺いますが、新幹線開業後に、観光客は確かに増えてはいますが、知事もおっしゃっているように、インバウンドの特に宿泊客などは目標に対して非常に厳しい現状です。今回行う諸々の改組を行うことで、インバウンドとそれ以外の観光客も含めて、今の福井の課題をどのように、どんな未来にしていくか。現状のその課題も踏まえて、このように強化していくというお話をいただけたらと思います。
[知事]
観光については、基本的には順調に推移していると考えています。北陸新幹線が開業して一年間のお客様の入りの増も18.5%というところで高い水準ですが、直近の状況を見ても大きく落ちていません。18.2%、単月でとってもそういう状況にあると認識をしていまして、観光客の数も、いろいろな観光地でのお客様の数も、そんなに落ち込んでない、今のところ高止まりしている状況にあると認識をしていますので、以前も申し上げたと思いますが、福井にお越しいただいたお客さまの満足度が9割、1年以内にもう1回行きたいという人は5割など、特に福井のことを友達に推薦したいという、そういう意向も強いということは感じさせていただいているところです。
その中で課題があるといたしますとインバウンドです。また、一部の地域、例えば嶺南の西部の方で開業効果が薄いのではないかと言われるようなところがあるということは認識をしています。そういうことで、まず一つは、好調と言われていますが、この観光全体の動きを途切らさないということで、今ご説明もさせていただきましたが、プロモーションをこれからしっかりと、今後とも引き続きやっていきます。東京、首都圏もそうですし、東北地域もやらせていただきます。さらには万国博覧会を活用しまして、JR西日本ともタイアップをさせていただいて、万博プラスワントリップということで、万博に来た主に国内の人、外国人もいてもよいですが、国内向けにも万博と福井ということを、これはJR西日本、そして日本旅行は福井と和歌山と岡山だけをターゲットにしてやっていただいているということですので、そういった力も入れさせていただいています。またインバウンドのことで言わせていただいても、同じくJRと、ジャパンレールパスを外国人がみんな使って新幹線に乗るわけですね。ここのところで宿泊施設とセットにした商品をこれは福井県だけとJR西日本はタイアップしていただいて、やっていただくということも進めさせていただきますし、またこれはどちらにもいくと思いますが、はなあかりが非常に昨年好評でしたが、これも万博期間中に大阪から敦賀まで、これ終点になりますので、宿泊なんかもしていただけると思いますが、そこからお客さんが行きますので、新しく国内、そしてインバウンド向けにも力を入れていく素地ができていると思います。その上で予算の時にもご説明をしましたが、やはり構造的なところがどこにあるのかということを、データも含めて調査・分析をしていただく。大変県もお世話になっています。例えば観光ビジョンを作る時にいろいろとご議論いただきました。本当に詳しいですし、全国的にも著名な方が福井県にどっぷり浸かって、いろいろと調査・分析した上で施策に反映など、こういうことをやっていただき、またマーケティングの指南を業者に対してしていただくこともしていただけることになっていますので、こういったことをインバウンドを特に力を入れてやらせていただこうと考えています。
嶺南地域についても予算の時にもご説明をしましたが、青々吉日という嶺南地域全体で一つ一つのイベントがポツポツとあるのではなくて、全体としてお客さんが行ったり来たりできるような、もしくはそれ一本で青々吉日というネーミングで売り出せるような、プロモーションできるような体制を引き続きしていますし、また2月20日からは若狭湾プレミアムリゾート構想の公募をかけています。9か所の場所を紹介していますが、おかげさまで現在6社が11か所に、重なったところもありますが、非常にみなさん興味を持っていただいていると思いますので、6月まで募集がかかっています。7月からは優先事業者を決めて、具体的な内容の話し合いに入っていきたいと思っています。
また、武生や鯖江駅周辺もしくは福井駅前の商店街のところが、少しお客さんの足が減っているというようなこともありましたので、これも9月補正からやらせていただいていますが、商店街自らが成長するための計画を作ってもらって、消費喚起もやらせていただいたおかげで、この間の1周年の時、雨の日でしたが、鯖江の駅前にも人が多かったと思いますが、非常に賑わいが出てきている。そういうことを繰り返していって、色々考えていただくということは、盛り上げていくための1つの方法だと思います。具体的な方法も含めて、少し足らざるところ、こういったところ、インバウンドも県内全体も強化しながら、さらに引き続き首都圏、関西、万博周辺、こういったところも、インバウンドは特に京都駅に、日本旅行のジャパンレールパスをもらいに来る場所があるのですが、そこに福井県のコンシェルジュを設けることもやらせていただいて、福井県いいですよということもやっていこうと考えています。
[記者]
もう一つの柱の一つに子育て支援の強化があると思います。ふく育県推進チームについて伺います。トップについては鷲頭副知事ということでしょうか。
[知事]
そう考えています。
[記者]
チームメンバーですが、どんなメンバーで何人ぐらいの規模感を考えていますでしょうか。
[人事課長]
こども未来課をサブリーダーとして考えておりました。庁内の関係課、未来戦略課や福祉関係課で、13名程度で考えています。
[知事]
こども応援ディレクターにも中でサブリーダーになってもらったりしていきます。
[記者]
課長級によらずということでしょうか。
[知事]
主に管理職です。管理職を中心にやっていきます。
[記者]
そういった部局を横断して、こういったチームを作ることのメリットと、具体策についても教えてください。
[知事]
一つには、先ほど申し上げましたが、量的なものです。お子さんが2人目からは幼児教育無償化とか高校授業料無償化とか、いろいろなことをやってきました。それはそれなりに行くんですが、それはだいたい量的には、やれることはありますが、財政的な限界もあります。
もう一つ大切なことは、子どもを真ん中に置いた時、もしくは子どものいらっしゃるご家庭を真ん中に置いた時に、その人たちがかゆいところに手が届くように、あのところは少し切れ目がある、ここが足りないということがないようにしていくことは、子育てをする上では非常に重要だと。特にいつも申し上げていますが、Uターンもしくは福井県で生まれて育って、そのまま福井という場合はお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんが家にいることになるわけですが、そうではない、Iターンの場合はそういったいろいろなサービスの切れ目というところが意識されるということをよく伺いますので、このチームを立ち上げることで行政として、切れ目なく子ども中心により良い子育てができるようにしてきます。
またもう一つは、こども応援サポーターというのを作らせていただきますが、これはこども応援ディレクターが、日頃からいろいろ人脈を培っていますが、まさに今申し上げたような、いろいろな境遇にある子どもたち、もしくはそのご家庭があるというところに寄り添う形で、その人たちの目線で、その人たちに何かをしていくとしたら、行政としてやっていくということもあるでしょうが、その方々と一緒になって、隣のそういう子どもたちもしくは他に県内でいるような子どもたちに対して手を差し伸べていけないかという、官民共創の取組みをしていきたいと思っています。
[記者]
資料11ページの女性管理職の登用促進です。新年度の登用数、過去最多の127人ということで、今年度を抜いて最大になりました。割合でいうと25%で1つ節目ではないですが、これは何か県の目標値、何かの計画に照らして、目標をこれだけ達成したという見方はできますでしょうか。
[人事課行政経営・人材マネジメント室長]
これは行財政改革アクションプランの中での目標値です。
[知事]
これは令和7年度中に25%というのが目標でしたので、それを達成するということになります。
[記者]
最後に1点だけお願いします。資料15ページのフリーアドレスですが、本当に今各課を見ますと、雰囲気がすごく変わったなというのは実感します。改めてフリーアドレスを導入して、どんな成果が上がっているのかということと、庁舎全体をフリーアドレス化するのは、かなりの費用がかかっているのかというところで、費用についても、全体でどれだけかかったのかというのも教えてください。
[知事]
費用は今、調べてくれると思いますが、効果は職員はまず部屋が明るくなり、そして日頃お話ができていない人とお話ができる環境が常にできますので、そうすると気分転換にもなりますし、また課の中のコミュニケーションも取れて、明るい雰囲気で仕事ができるということで、非常に好意的に受け取っていただいている方が多いと思います。
そしてお金がかかるというところは当然ありますが、ただ相当古くなっていた机や椅子などを一旦ここで取り替えて、なおかつ書庫なども取り払うことで非常に広いスペースを確保できるということで、今までだとパソコンの場所を置くところも本当に狭い職場環境だったところを広々とできているということでも、この県庁を有効に活用するという意味でも非常に、結果的にというところが大きいですが、本当はフリーアドレスは職場環境整備と思って職員向けに最初は始めましたが、やってみるとまさにデータ化してペーパーレス化が進んで、自宅でもテレワークができるようになり、先ほどのハイブリッドワークもできるようにと、ものすごく大きな効果を生んでいると感じています。そういう試算はしていないと思いますが、非常に効果大きいと思います。変な話ですが、市町から来ている職員のみなさんと喋ったりすると、もう帰りたくないとか帰れないというか、こんな環境で仕事をしてしまうと戻りたくないぐらいの勢いでお話をされますから、比較はできないのですが、比較ができる環境にある方は実感をものすごくされているように伺っています。
[人事課長]
先ほどのフリーアドレスの数字ですが、今年度まででかかっているコストは約2.6億円です。
[記者]
観光誘客についてお伺いします。今後、新幹線開業というところのメディアへの露出効果というところが薄れてくると思います。そこで2年目というのは、自力での誘客とリピーターの獲得というところ、すごく大事な課題になってくると思いますが、その点について、組織改正も踏まえてどのように強化していくかお考えを教えてください。
[知事]
はい。おっしゃる通りで、最初のご祝儀相場ではないですが、1年も経ってくると珍しさはなくなってくる。今までは「知られざる福井へ」ということで、「知らなかったね。行ってみようよ。」という感じがありましたが、そのところが普通に「あ、福井ね。」という感じになってくる、御祝儀相場のようなものがだんだんこう薄れてくるということはあると思います。しかし一方で、先ほども申し上げましたが、非常に福井にきて良かったと言われる方が9割いらっしゃって、また1年以内に来たいという方は5割いらっしゃる。もてなしとか、また福井のいろいろな観光地。来られた方と私も何人か話していると、みなさん、「福井って行くとこいっぱいあるんですよね。」っておっしゃられますね。行ってみるとどこもとてもいいと。永平寺も一乗谷も、そして恐竜博物館も東尋坊もそうだし、三方五湖も打刃物もそうだし。大野も良かったとか、このようにおっしゃられます。そして北潟湖のあたりもいいとかですね。本当に、来て、また発見して、あ、ここ行かなくちゃというようなこともお話をよく伺いますので、まずおいでいただいたというのが非常に次につながる効果になったと思っています。その中で県議会でもご議論いただきましたが、プロモーションを引き続きやらせていただく。最近、東京に行っていろいろな方にお話を伺っても、東京で福井のこと、駅を色々歩いててもよく見るのよねと。これは私どもがいろいろと努力をしてきた、こういったことの結果でもありますが、おかげさまで、例えば銀座の食の國291も、お客さまの数も、売り上げもしっかりと伸びてきている。2年目ですが、ご祝儀相場から次に福井がいいところというように変わってきて、さらに引き続きプロモーションを首都圏、また東北地域でもやらせていただく。大宮ももちろんですし。こういったことを関西万博も含めて、いろいろなイベント事がありますので。そういったところへお迎えに行く、こういうこともやらせていただきます。あと新幹線の次の大きなイベントごととしては、中部縦貫自動車道だと思います。今、開通時期が未定になってしまったので先に伸びましたが、いずれにしてもこれは何年かのうちには開通するわけですので、今度は人だけでなく、物も運んでくれる。そして今、敦賀で乗り換えが増えて、中京は遠くなったという感じになっていますので。ここのところが無料の高速である中部縦貫自動車道が繋がっていくというのは、とても効果が大きいと思います。そういうイベントごとも活用しながら引き続き、あとは受け入れ側。今のところ、例えば大きなイベント、桜マラソン、大きなコンベンションを開こうとすると福井周辺だけでも2,000人分の宿泊施設が足りないという話がございますが、現状を伺っているだけでも100室以上のホテルの新設計画というのが、5か所はあります。さらにもっといろいろな形で、上質な宿も含めて計画がございます。こういった受け入れの整備、インバウンドを含めて引き続きやらせていただく。例えば民宿リニューアル。これも全然手を緩めないで、令和7年度も39件、予算の枠を持たせていただいて、現実に手が上がってきています。投資をすることで、福井の周辺が賑わった。結果として、また投資をしたいという人が再開発を含めてどんどん出てきている。この良い循環をこれからまた続けていくことが、次の観光誘客にもつながるとも考えています。
[記者]
資料8ページのところで、ドローン活用ディレクターのお話がありましたが、全国的にも珍しいと思いますが、他の自治体で例はあったりするんでしょうか。
[知事]
そもそも、ディレクターをやってるところがないと思いますが、ドローンを活用している自治体はいくつもあると思います。福井県のように、例えば、災害が起きた時に自動で河川なんかを遡っていって、もしくはそこを使って孤立集落のところへ行って、自動的にこう写真を撮ってきて、状況を見て帰ってくるとかということまでやってるところは本当に少ないだろうと思います。その上で、最近、私が感じましたのは、土木部に、土木事務所だったり、本庁にもいますが、本当にドローンの得意な職員が増えているわけです。そうすると、次々とうまくなっていくというか新しいことを考えたり、こんなこともできるんですよとか。あんなこともできるんですよ。それがある意味珠洲市で上からあの写真一枚というか、だーっとこう撮っていくと、どこにどれだけ土砂があって、これはどうすればいいかっていうこと、もう一目でできていくようになります。こういった新しい発見が非常に多い。その中でも、だからやる気があってぜひやりたいと言っている職員がいたので、こうしたドローン活用ディレクターというのをやらせていただきます。裾野も広げていますが、それをさらに高みに持っていくということが。これによって本当に全国でもトップクラスで進んでいくのではないかと思っています。
[記者]
今おっしゃっていただいた災害調査とか、朝井主任を中心にかなり積極的に先進的に取り組んでいるかなと思いますが、そこに書いてある物資の輸送というところは、現状どういう取り組みをされているのかというところと、今後どういう展望を描いているのか教えてください。
[知事]
今は、たぶん、現状でも商業ベースでやっていただいているのは、西濃運輸が敦賀でやられているというところかと思いますが。こういった災害時には、例えばですが、食べるものを大量に物を運んでいくという発想だけではなくて、通信ができるように、例えば衛星電話、これを持っていって置いてくるということだったり、ちょっとしたお薬を運んでいくとか、非常に命綱としてはとても物資の輸送というのは、大小に限らず重要な場面があります。そういったことを、できる範囲でやっていくということをまずはやっていきながら、最終的にはこれは規制緩和が必要なので、非常に難しいところもありますが、街中をドローンで物を運ぶというようなことにも広がっていくのかもしれません。ここのところは災害現場をある程度念頭に置きながら考えておりますので、先ほど申し上げたようなことを、中心に考えていくと思っています。
[記者]
似たような質問で申し訳ないですが、改めて新幹線開業一年で、どういった成果と課題があったと知事が受け止めているかお伺いします。特に今回、新幹線対策全般の課を再編したというところにも課題感の認識もあるかと思いますが、そのコメントをいただいてもよろしいでしょうか。
[知事]
今回、この交流文化部の課の再編は大きく言うと新幹線開業課といって、開業までにやらなくてはいけないことを徹底してやってたところを少しバラして、全体として平常運転の方に持っていくというようなことでやらせていただいてます。開業効果につきましては、先ほど申し上げましたが物量のところは、全体としても2割近くのお客様が増え、しかも直近の1月16日から2月15日の間でも全国から約18%のお客様が増え続けているというところ。今日も新聞報道ありましたが、金沢・福井間も25%増えている、これは昨年の開業日直後と比べても減っていない。このような状況が続いているということは、一つ大きな効果であると思っています。それだけではなくて、本当に新幹線は気持ちも運んでくるとも時々申し上げていますが、県民の中で幸福度ランキング日本一というのは12年連続ということで昨年の秋に発表いただきましたが。それだけではなくて、新幹線開業後、県で幸福を実感していますという都道府県ごとの全国アンケート、この中でも例えばデジタル庁は一昨年が12位だったのが4位に上がるとか。そして、ブランド総研は19位が5位に上がるということで、幸福実感、幸せ実感も上がってきていることは非常に大きいと思いますし、先ほど申し上げているように、新幹線が来るぞということで投資をさせていただいた。福井駅前を見ていただくと再開発ができて、マリオットのビルができ、開業とともに人がバッと押し寄せた。結果として、また次の再開発が南通りの方にも広がっていく。ホテルも100室以上のところが少なくとも5か所は声が上がってきているとも認識をしていますし、それ以外にもたくさんの投資が行われていく。こういった「投資と、賑わいの好循環」も生まれてきていると認識をしています。
[記者]
今後の一年の成果も踏まえつつ、今後必要と思っている課題感的な目線も伺いたいのですが、例えばここにもありますとおり宿泊・周遊推進室の設置もあります。県内にまだまだ宿泊施設が足りないというのは、知事も認識されてると思うので、そのあたりのコメントいただいてもよろしいでしょうか。
[知事]
これも先ほど申し上げましたが、現状において、例えば桜マラソンであるとか、大きなコンベンションを開くと宿泊施設が足りなくて金沢に泊まらなくてはいけないというお話も伺うところでして、1,000人から2,000人分が足りていないとも言われています。これについてもすでに表明されているのを足してみると県内で2000人分程度のホテルの宿泊施設のプラスがあると、ホテル・旅館という業種で言えば、今が10,000人ちょっと、10,156人。令和5年度末だったかと思いますが。そこから2,000人増えるというと2割程度はこの2年ぐらいで増えますので、こういった課題についても、ある意味先ほどの投資と賑わいの好循環という中でうまく生まれてきている。あとは、土地の値段もそういったトータルで見た時に土地の値段に出てきますので、県内でも地価が全国的に高い方で上がっているということがありますので、こういった、いい方の効果が次々出てきているなと思います。課題は先ほど申し上げたインバウンドであったりとか、県内の各地域にそれを広げていくということですが、これについては嶺南地域については若狭湾プレミアムリゾート構想もやらせていただきますし、また商店街対策も、人が行っていないところはやらせていただいています。その他の観光地の磨き上げもまだまだ続きますので、例えば大野の六呂師高原も、もう間もなく夏にはオープンをいたしますし、東尋坊も商店街の賑やかさが少し足りないと言われてましたが、今年度、来年度中には商店街がばーっと綺麗になりますし、ビジターセンターもあと3年くらいのうちには出来上がるとか、駐車場も周辺全部変えてくるとかですね。一乗谷も少しずつよくしていきたいと思います。金ヶ崎やアリーナなど、いろいろな構想も持っておりますので、そういったことを含めてさらに投資もしながら賑わいを作っていきたいと思っています。
[記者]
聞き逃していたら恐縮ですが、女性管理職のところで今回過去最多の率と人数とおっしゃっていましたが、これは全国何位とおっしゃっていましたか?
[知事]
全国2位ですね。
[記者]
令和7年度ですか。
[知事]
令和6年度です。7年度はまだ出ていませんので。
[記者]
このように平成30年度と比べると、倍以上ということで、かなり増やされていると思いますが、このように増やされた。どういったことを工夫だったりとか、取組みとしてやってきた結果がここまで増やせたとお考えでしょうか。
[知事]
これはもう、私が知事になった時からです。常に申し上げてまいりましたが、管理職はまず職員の男女比というのがありまして。職員の中で全ての職場を入れれば、先生は除きますが、病院も含めると、43%が女性職員。看護師なんかを除いた病院を除いても32、33%が女性職員の中で10%程度だったんです。ということは、やはり女性の活躍、もしくは職場で必ずしもどんな障害があるかわかりませんが実力が発揮できているのかという課題というか認識を持ちまして。しかし一方で、じゃあいきなり管理職にすればいいのかといえば、それは経験のないものをただやみくも上げていくというのは、この県庁組織は当然のことながら県民のみなさんのために働く組織ですので、適材適所でなければいけないということで。当初はもちろん、課長、参事といった管理職を増やすということもやりましたが、今日もご説明した通り、予備軍であるグループリーダーや課長補佐の経験をしっかりと積んでいただく。また女性職員のみなさんにもぜひ管理職を目指そうといったことも含めてお話もさせていただきながら、やらせていただいた。そういうことで、徐々に徐々に、急にいきなり増しているわけでありませんので、非常に時間もかけながらただ前向きに、やはり女性がマイノリティになっている、そこのところをしっかりと課題として認識しながらやってきた、適材適所でやってきた結果と思っています。
[記者]
人事異動に関して今回部長級で危機管理監の中嶋さんが役職定年の特例を使ってもう一年続投されると、交流文化部長は定年の延長をされるんですか?
[知事]
そうですね、定年の延長です。
[記者]
4年目に突入されるということで経験を重視されていると思いますが、管理職がこれだけ長く務めるということは、管理職の人材不足というか、部のトップを務める人材の育成が不十分なことが影響しているのか、続投させる意味合いを詳しく教えてください。
[知事]
おっしゃられるようなご主旨を言われるということがあるのかもしれません。もう、まさに適材適所。この方を今はこの人しかいないだろうと。こういうことで配置をさせていただいています。西川部長はもちろんのことながら、交流文化。もう本当に新幹線開業もしっかりとやり遂げていただいて、今申し上げているように大変お客さまにおいでいただいている。素晴らしく明るく、組織も統率力も強くて、今はアリーナ構想が佳境に来ておりますので。そういう意味では余人を持って代えがたいということかと思っています。それから中嶋危機管理監。彼もこの能登半島地震の時も自ら早い段階で現場に、特に奥能登豪雨の時にはすぐに現場に行って現場を見て、必要な対応を取る。最初の時には女性職員をいの一番に送り込むとか、やはりエキスパート中のエキスパートだと思っています。今年どうするのかということも考えましたが、やはり、もう一年は彼に託すのが一番いいだろうと。やはり県民のみなさんに対して最もパフォーマンスをあげる組織であるべきだと思っています。伊藤さんももちろんですし、原子力のところで、ここのところも今、非常にいろいろな課題がありますので、彼は技術面の要ですので、いつもいろいろな議論しますが、事務的なことの流れは私はわかりますが、技術がこれ大丈夫かというときに、彼が一番詳しくて。当然詳しいですが、もういないと本当に生き字引というような方ですので。もちろん育っていますが、やはりこれと思った瞬間に少し違うんです。だから今はそういう状況かなと。産業支援センターも今、構想的にいろいろ考えていて、今年一年はぜひやっていただきたい、やはり余人をもって代えがたいところがあります。そういうポイントポイントだけですので、最後は定年そのもの、役職定年という制度がありますが、これもまだ10年も20年も先だと思いますが、いずれそういう時代が来る。65歳定年になっていくので、最後が65歳になっていくのだと私は思っています。そういうことから言うと、何も60歳で役職定年でなければいけないということではなくて、適材がいれば適所に配置するということは、私はそれほど時代的におかしくないと認識をしています。
[記者]
今回派遣とか退職とかも含めて、県内の市町に特別職というか、副市長とか副町長の形で、まだ議会を通っていないところもあるかもしれませんが、行くという方向になって、これが結構増えていまして。こちらの調べだと、17市町のうち過半数は超えたのではないかなと思いますが、これは首長さんから要請があって派遣してるのだろうとは思いますが、これの県側から見たメリットとか、特別職に県庁職員を置いていることの連携面とかを教えていただきたい。
[知事]
これは事実関係から申し上げれば、全て当然のことながら、先方からたっての願いということで言われまして。目の前のことだけを言うと、私たちもとても困っていまして、優秀な人材を私どもも選んで送らせていただきますので。本当の目先だけを言うときついなと思うところはありますが。私は総務省時代も副知事時代も、福井県庁でこう仕事をさせていただいていますが、県に対して市町のみなさんがとてもなんていうんですかね、こう頼りにしているというか、寄りかかるという頼りではなくて、県庁がよくやっているとか、職員がよく頑張っているという姿をとても感じていただいているようには思います。市長や町長とお話していても、県がよくやっているということを、もういろいろな時に伺わせていただきます。そういう中でなんとか私も国から職員をお借りしてきますので、そういうのと同じような思いなんだろうなというところです。みなさんのそういった要請があれば、あまりどんどん出すと本当に大変なので、そういうところは我慢していただいたりとかしつつですね、今はこの数になっているということです。私どものメリットとしても、やはり県でいるよりは範囲は狭いが責任の高い部署を任されるということが非常に多いので、そういうことからしても県に帰ってきてからの動き方が違うなと、経験とはこういうことだと。私もそういう人生を歩んできましたので、ポジティブに考えて、目先は大変ですが戻った後のことを思いながらやらせていただいているところです。
[記者]
関西電力のロードマップ見直しに関して、知事は先の県議会で、自民党福井県議会の総括質疑で、できるだけ早く武藤経済産業大臣と関西電力の森社長と会って、最終的に県としての判断をしたいというような旨の答弁をされました。3月はもう2週間を切っているが、その後、日程の調整は進んでいるのですか。
[知事]
今は本当に日程調整中で、大臣は特に、本当に今、もうご案内の通りの国会状況、それから外交も今本当に難しい日米関係もあったりして、本当にお忙しくて、日程が決まらないというのが現状ですので、いろんなリモートもあるかもしれないけど、とにかくしっかりと考えを確認できる体制をとっていかないといけないなということを含めて、さらに調整中だというところです。
[記者]
主に武藤大臣の日程調整でスケジュールが確定していない状況と推察しますが、気になるところが、年度内という一つの区切りがあったと思います。知事とすると、年度内までに実効性があると判断できなければ、基本的に関西電力の社長が言っていた通り、40年超の3基が止まるという認識だと思うが、この取り扱いはどうなるのですか。
[知事]
ここは特段考えていないというか、考えていないというのは変ですが、まず、年度内で日程を調整しているということ、それと、仮に4月の初めにずれ込んだとしても、これはもう物理的な日程の調整の問題なので、そのことをどうというほどのことはないかなとは思っています。
[記者]
今の発言であると、あくまでこれは日程上の調整の問題という考え方でよろしいですか。
[知事]
まさにそうです。
[記者]
できるだけ年度末にということですが、今の国会状況であると、なかなか3月中というのは難しいのではないかなと思ってしまいますが、現状、知事の考えとすると、前回のロードマップのように、直接福井に来てもらって、森社長も含めて3者でそれぞれ面談するという形式を望まれているのか、それとも、やはりそういった日程の中では、リモートであったり、もしくは知事自らが経済産業省に行くといった、今のところどういった考えですか。
[知事]
いずれもあると思います。おいでいただくというのが、本来、国とか、関西電力の思いをしっかりと伺えるという意味では、最もよろしいとは考えますが、しかしとはいえ、本当にこの時期になっているということは否定しがたい事実ですので、そのことをあまり他にも本当にお忙しいみなさん、関電の森社長もそうだが、そういう中なので、ここは少し状況、幅を広げて、とにかくしっかりと確認ができるような、そういう場面を持つということが大事かなと思っています。
[記者]
あとは調整の段階なので、あまり年度末の止めるとか止めないとか、そういうところにこだわらないのであれば、極力年度末という考えではあるが、年度内に必ずというような考えでは現状ないという認識でよろしいですか。
[知事]
物事は相手がある話なので、そんなに物事にこちらが最初から優先順位をつけて、これの次はこれで、これでとかをやっているわけではないので、全体として考えて日程はセットしていくのだと、もしくは持ち方、リモートなのか、私が東京行くのか、おいでいただくのか、いろいろあると思うが、そういうことも含めてトータルで一番いい方法でありますが、基本はもう年度内、それはそういうことだと思います。
[記者]
国会状況も承知しているし、先日も武藤経済産業大臣がアメリカに行かれたり、お忙しいのは重々承知ですが、とはいえ、国側も、年度末までに福井県が実効性があると判断しなければどうなるかというのは、当然見直しの段階でも承知していると認識しています。結局、原発立地の福井県を軽んじているのではないかとも捉え方によってはしますが、その点はどう考えますか。
[知事]
あまりそういう、いつもそんなことをされていれば、私もいい加減にしてという感じになりますが、今は本当にギリギリいろいろと、仲良くと言うと変ですが、しっかりと変な感情論を持たないで、やり取りさせていただいていますが、現実に大変な状況ではあるということであるので、あまりそういう、こうでなければいけないとか、そういうことを持ち込んでできるタイミングでもないなと思っています。しかしより良い方法がいいということから言えば、やはり姿勢を見せていただきやすいと言えば、おいでいただくということだとも思いますが、しかし今は少し、なかなか、私もいろいろ聞いていますが、難しそうだという気はしています。
[記者]
武藤経済産業大臣と森社長と会われて、知事は、今後、工程表の確実な実行、地域振興に関して責任ある対応という、この2点を確認していくという考えを議会で述べられていますが、具体的に、この2点について何が確認できれば工程表を受け入れられると考えるのですか。
[知事]
私が多分申し上げていますのは、関西電力に対しては、まず六ヶ所再処理工場の竣工目標に向かってどう対応するのかと、そして、稼働したとして搬出枠をしっかり確保していかなければいけませんので、その確保の話と、そしてロードマップの状況、これを、申し上げているのは、定期的に情報として流されるだけではなくて、しっかりと確認ができる、お互いに意思疎通が図れるような、そういった確認の仕方、仕組みを求めるということを申し上げていますし、そして地域振興について、これを絵に描いた餅にしない、財源、こういったものをしっかりと揃えていただくということについての話を伺おうと考えています。
そして、国に対しては、まずは六ヶ所の竣工目標を透明性を持って進捗管理をするとおっしゃっていますので、これをぜひ、そうするということを確認をさせていただかないといけないと思っていますし、また、搬出についても、これも量的にはかなり関西電力の分が多くなるので、国としても、こうした搬出についての関与、こういったことができるような枠組みというようなことを求めていくとも申し上げています。あとは、地域振興、課題解決について、政府一体で取り組む枠組みであったり、もしくは財源、こういったことについても話を聞かせていただきたいと考えているところです。
[記者]
例えば財源とか、地域振興に関して国側が取り組む枠組みとか、これはそういったものを作るという意思と覚悟が示されればいいと考えなのか、具体的なものが何か出てくることを期待しているのか、伺います。
[知事]
これは、相手がどのようにお考えになられるかだと思います。まずはそれを伺って、我々が考えていくということだと思います。
[記者]
14日に県議会で、ロードマップに関する意見書の賛成討論の中で、ふくいの党から、福井県が主体的に高頻度で六ヶ所の進捗状況を確認する枠組みを作って、そこで六ヶ所が再延期される可能性が高い状況になったら、その時点でロードマップの実効性が失われて、美浜3、高浜1・2の3基の停止の約束へと戻ってくる認識でいることを賛成の条件としていました。この考えについて、現状の知事の認識を伺います。
[知事]
これは、ふくいの党の考えとして、そういうところが守られれば賛成するんだというような話をされていたんだと思います。この後、ロードマップが破綻するということは、私ども仮定の話なので、そういったことについて答えをするということは避けたいと思いますが、しかし一般論として言えば、前のロードマップがあって、それがうまくいかなくてこういうロードマップがあってということをしているわけであるから、我々としては、もしもそういうことがあれば、普通に考えると、どうするのかということは、当然のことながら、関西電力の方からいろいろと話があるのだろうとは認識をしています。
[記者]
どうするかというのは、3基の運転をどうするかというところですか。
[知事]
3基の運転なのかというのは、その3基の運転が直接何に関係しているのか、私も正直言って、覚悟があるということはよくわかります。1基止めるということが非常に大きな、これは電力の供給の面でも非常に大きいと思いますが、そして関西電力の会社としても大きな決断だと思うので、それは何であるかはわからないですが、当然のことながら何らかの、しかしいずれにしても、最後は管理容量いっぱいになれば止まるということであるので、方向は同じ方向にいっているので、いかに持ち出すかというのは、これは関西電力も含めて、国ももちろんですが、みんなが共通で求めていることだとは思います。
[記者]
一般論として言うと、破綻したと考えられた場合には、関電から何らかの覚悟が示されるべきだと考えますか。
[知事]
というか、これまでもそうだったということを申し上げています。
[記者]
今も知事の話で、管理容量がいっぱいになったらいずれにしても止まることになるんだと、県議会の議論でも繰り返し答弁されていたので基本的な話だと思いますが、これはあくまで一般論であって、一方で、乾式貯蔵施設の計画を懸念する声は、県議会でも出ていて、フランスに搬出することによって2030年までこぎつければ、今度中間貯蔵が破綻したからと理由をつけられたら、それを例外に当たるとは一言も言っていないので、なんとでもできる話です。
これについて、県から釘を刺さないのかと聞かれても、毎回約束は守られるべきものだ、当然守られると承知しているということで、積極的に釘を刺す姿勢は示されていないが、なぜですか。
[知事]
乾式貯蔵の話は今していないので、全然乾式貯蔵の容量が増えているわけでもありませんし、今の管理容量は今の管理容量であって、その乾式貯蔵が増えたらと言っても、その増えた議論になっていませんので、今のまま行けば止まるということだと思います。
[記者]
議論してないということではなくて、もう計画が進んでいますし、そうなった場合、物理的にこれは確実に増えるわけです。
[知事]
事前了解をすれば増えるのであって、事前了解しているわけではないので、だから、そのあまり仮定に仮定を重ねるのはちょっといかがなものかと思います。
[記者]
そもそも(令和5年)10月の記者会見で、知事はバッファーという考えがあってということ、立地の首長からそういうことを言われたということの話の中で、いくつか言及もあったが、そういったところから、将来的にそういうものを想定しているんだなというのはこちらも伺えるわけで、今それは関係ないというのは、それは容量と直結する話なので、それはちょっと、切り離しすぎと思います。
[知事]
いや、くっつけすぎのようにも思いますが、バッファーと言ったかもしれませんが、それは多分誰かの言葉を引用しながらだと思いますが、それは乾式貯蔵の議論なのか。事前了解するとかしないとかいう議論の時に、そういう議論が出てくるということは、ないとは言いませんが、そういう議論としては、乾式貯蔵が認可されているわけでもなんでもないのに、今それを言われても、管理容量を超えては止まりますよねということは普通の話だと思います。
[記者]
少なくとも県議会の議論の中で、そうは答えていませんでしたが、それはどうしてですか。
[知事]
いや、そういう質問でなかったのかもしれませんが。いずれにしても、乾式貯蔵の議論を今しているわけではありませんので。
[記者]
私も乾式議論の議論をしているわけではなく、関係する部分について聞いているわけで、少なくとも、乾式貯蔵の議論も今後進んでいくわけで、その時の例外とか…。
[知事]
「わけで」って言われているが、仮定ですよね。
乾式貯蔵の議論は、答弁申し上げているのは、今回のロードマップのことを認めなければ乾式貯蔵の議論には入りませんっていうことは答弁に明確に申し上げていますので、今は乾式貯蔵の議論の前の段階の、今の管理容量で当然止まるという話だと思います。もっと言うと、乾式貯蔵のところだって、関西電力がそれを増やさないというか、管理容量を増やして使わないっていうことは言われているということを申し上げているっていうことです。
[記者]
とりあえず、そのことは分かりました。
前回、関西電力のロードマップが出てきて、これを実行するのは、確かに知事おっしゃる通り国と関電ですが、中間貯蔵施設の県外立地という、使用済燃料の県外搬出を求めた福井県の要求に沿うものかどうかということを知事は一旦判断されたわけだが計画が破綻をしました。それも全く予期できぬ事象によって破綻したわけではなく、散々指摘されてきた六ヶ所再処理工場の操業延期という点で延期されたということで、これに関しては知事の総括、反省が必要だと思いますが、これをどう分析されているのですか。
[知事]
以前、確かに中間貯蔵施設を2023年末までに計画地点を確定するというような議論があって、それがロードマップの方に切り替わってきたと考えますが、その時にも申し上げたと思いますが、福井県が求めているのは、使用済燃料を県外に搬出する、使用済燃料の発生量に比べて十分な量を県外に搬出するということを継続的に行うことの方が、中間貯蔵施設そのものを作っていくことの約束よりは、ある意味合理性が高いかなということでロードマップというのがあるんじゃないかということで認めさせていただきました。
それに対して、おっしゃられるように、国と関西電力がそれを守る、なんとか実現するというのがミッションとしてあって、結果としてできなくて今回の新しいロードマップの議論になっていると。その前のロードマップが守れなかったことについて、私は議会でもちょっとなんて言ったか言葉は忘れましたが、県民のみなさんに対しては、自分が至らなかったところの、申し訳なくと言ったのか、ちょっとそんなことを申し上げたと思いますが、そういった状況にあるとは思っています。しかし、今回はまた新しいロードマップの議論なので、それについてはしっかりと国に対して責任を果たしていただくという必要があると考えています。
[記者]
今議会で知事が答弁されていたと思いますが、ロードマップの実効性について、国の使用済燃料対策推進協議会の幹事会、これを見ていくと答弁されていると思いますが、私も2月、3月の議事録を見て、基本的に中身としては、事業者側が説明をして事務局がそれに対してQAするというような、基本的には多分そういう中身なのかなと思ったが、知事が幹事会でどのような情報を期待されるのか、どういう情報を持ってロードマップが遅れそうとかというのを判断しそうなのか、どういったものを想定されているのか伺います。
[知事]
直接的には、日本原燃は、事前に説明の全体計画というのを作って、それに基づいて1項目1項目やっていくわけなので、少し遅れていたり、何かがちょっと早くなっていたりで、全体として見ると早いかどうかというのは結果として公表しているということです。なので、私どもが言っているのは、関西電力との間でも、全体としてロードマップがどこまで実行されているか、そういう状況を分かるような、定期的に確認する仕組みを求めているわけです。
だから、我々も同じように、これ遅れているのじゃないのとか、これ大丈夫なのっていうことをきちっとやっていかなくちゃいけないので、そういうふうに意思疎通が図れる仕組みを考えるべきだと申し上げています。
[記者]
それは各工程の工事の進捗のことをおっしゃっているということでよいですか。
[知事]
それに限らずだと思います。もちろん、原燃の方の工程がどうなっているということもあるでしょうし、その工程が遅れているだけじゃなくて、議会でも議論になったが、現状では関西電力から40人精鋭部隊が送られているとおっしゃっていましたが、それをもしも遅れ気味だったら、今度それをどう対応するのかっていうことも、関西電力との意思疎通ではやらせていただくということになると思います。
[記者]
去年の8月、日本原燃が竣工目標の延期を発表した際も、原燃側は直前まで目標を維持していたというか、ここから頑張れば、急げば間に合うみたいな説明をずっと昨年もしていた中で、原燃の説明でなかなかそれを判断するのは難しいのかなというような気もしますが、県としてそこはどのように考えていますか。
[知事]
これは今回の議論の中でも明らかになっているのだと思いますが、日本原燃は、前は間に合う間に合うというだけで、どこまで工程が来ているかということは発表していませんでした。それに対して今回は、事前にこういう工程で行きますということを見せながら、今ここまで来た、ここまで来たということを確認しているわけで、こういうところが大きく違っているようには思っています。
[記者]
ロードマップをめぐり議会側とか県側にも、原子力発電に反対する市民団体などから賛否抜きにして県民説明会を開催してほしいといった要望もあったのではないかと思います。こういった声があることへの受け止めと、現時点で開催予定はないのかなと思いますが、開催しない理由を教えてください。
[知事]
これについては、福井県はもうこれまで50年以上にわたって、様々な形で原子力行政というのを進めさせていただいています。もちろん県民向けの説明会を開いたこともありますが、そういう中で、今回について申し上げれば、通常の場合は、例えば県議会、それから立地の町、またこれらに関係のあるそういったみなさんも属される原子力環境安全管理協議会、こういったところでご議論をいただいて、それをしっかりとまとめさせていただいて判断をさせていただくということなので、今回も、その手続きに則って、やらせていただいていると申し上げていますし、私は考えています。
[記者]
現状、県内での議論は尽くされ、今後は関西電力の森社長、武藤経済産業大臣と会った上で判断するという結論に変わりはないということでよろしいですか。
[知事]
これは県議会でも、またみなさま方にお話をさせていただくときにも、そういうふうに申し上げています。
[記者]
当初ロードマップが履行不能になったのも、また今回、再処理工場に懸念が相次いだのも、そもそも中間所蔵施設という約束が出たのも、今まで全て再処理工場が完成しないこと、ひいては国の核燃料サイクルの輪が閉じないことが要因にあるのではないかなと思います。この栗田知事の時代から続く県外搬出問題は、県外搬出という小さな事例に矮小化されがちですが、核燃料サイクルがうまくいってないことの象徴事例のようなところがあるのではないかというふうに感じるところです。この1ヶ月間、特に再処理工場を中心に議論してきたことを踏まえて、国のサイクル政策への現状でのご認識等を伺います。
[知事]
まさに、いつも申し上げていますが、最大の課題は、国の核燃料サイクルを、一歩でも二歩でも前に進めていただくことだと認識をしています。今回のことに直接関わることで言えば、その中でも大きな全国的な課題だが、六ヶ所再処理工場の竣工をいかにして成し遂げるかだと思っています。
元々栗田知事が、中間貯蔵施設が要ると、使用済燃料を県外に搬出すべきだと、こういうふうにもおっしゃられたのも、平成8年の時点でしたが、平成5年度に着工した、六ヶ所再処理工場の竣工時期の延期が出てきた、ここから始まっているので、言ってみれば30年近くにわたって、そのことが進捗していない、極端に言うとしてないということであって、もちろん物は出来上がってきて、かなり審査も進んできているということで言えば、あまり1か0かという議論は私は正直言って正しくないと思いますが、結果として竣工していない、だから搬入ができない、処理ができていないことが大きな原因だと思います。
そのため、国に対しても、これは今回のことに限らず、私が知事になって以降、常に申し上げているのは、この核燃料サイクルをしっかりと回していけるように、まずは六ヶ所再処理工場の竣工に向けて、国は、エネ庁に限らず、規制委員会も、これは安全性を緩めろという意味ではなくて、合理的、効率的な審査というやり方もあるんじゃないかということも含めて申し上げて、政府一体となって取り組むべきだということも申し上げています。もちろん最後はバックエンドの問題もありますが、こういった核燃料サイクル全体を、しっかりと国、事業者には進めていただく必要があるということを強く思っています。
[記者]
北陸新幹線の延伸のことでお尋ねします。小浜・京都ルートは知事がおっしゃっているようにこれから進んでいくと思いますが、この間の馳知事の発言であったりとか、いま国会も、小浜ルートでとおっしゃった石破さんがああいった風にもなっていたりとか、西田参議院議員の選挙もあったりとか、いろいろ不安な要素はあると思いますが、今後どのように詰められていくか改めてお伺いできますでしょうか。
[知事]
これはいろいろな要素のことを言われましたが、それは一つ一つ遠因というか関係するかもしれませんが、あまり新幹線と直接絡めて議論するのは、私としてはあまり思っていません。とはいえ、やはり今、昨年の年末に整備委員会、西田委員会で、ルートを一本化して令和7年度中にも認可・着工という予算を取るというところに至らなかったということは、もちろん残念ですし、そのことが今のいろいろなご議論に結びついていると認識をしています。とはいえ、馳知事も前提として、京都のいろいろな課題が解決できないことが明らかになったような状態の時にはとおっしゃられておられていますし、また馳知事は、政府が決めた敦賀以西の案は小浜案しかないということも明言されていますし、さらには最近も言われていたと認識をしていますが、乗り換えなしで一日も早く大阪までの全線開業を求めていくんだということも明言を今でもされております。昨日も言われたか、一昨日または金曜日だったか忘れましたが、そういうような状況だと思いますので、これはまず、とにかく国・機構でしっかりと科学的知見に基づいて、京都府内・市内、こういったところの懸念事項をしっかりと客観的にみなさんに丁寧にご説明をして理解を得ながら、また財源の議論もとても大きいと思います。やはりこれからは国策、もう国土強靭化のための新幹線ですので、そういった意味では、ここのところもしっかりと国は財源の議論をしていただいて、そうすることで早く小浜・京都ルートによる新大阪までの全線開業に向けた認可・着工、これをお願いしたいと考えています。
[記者]
馳知事もいろいろと条件付きのようなことでは言っていますが、これまで中立なスタンスだったのが若干、米原ルートに足一歩ぐらい少し行ったというような印象を受けていますが、改めて知事としては、馳知事のスタンスが少し揺らいでいるというような、この現状をどのように受け止めていますか?
[知事]
これは以前も少しどこかで申し上げたかもしれませんが、政府・与党に対して、この状況をしっかりと前に進めて解決しないといけないじゃないかということの叱咤激励の意味が強いのだと思っています。
[記者]
先週以降、馳知事と電話やリモートなどでこのことについて何か意見ですとかお話しされたことというのはありますか?
[知事]
お電話しました。率直にいろいろと意見交換はしました。外で喋られている中身そのものではございました。
[記者]
それに対して知事が改めて私たちに言っていることと同じかもしれませんが、馳知事にどういうメッセージというか、どういったことを話されましたか?
[知事]
あまり電話の中身のことを一々のことは覚えていないのもありますが、人との電話の中身をそう申し上げることはよくないかなと思いますので、あまりは申し上げませんが、とにかく小浜・京都ルートで一日も早く大阪への全線開業、一緒にやりましょうねと申し上げて、その電話の後も外で馳知事は、乗り換えなく一日も早く大阪までの全線開業が必要だとおっしゃっていただいているので、それは変わらないとおっしゃっていますので、気持ちは通じているのだろうと認識をしています。
[記者]
関連の質問になりますが、本日の一部報道で、富山県の新田知事も現行の小浜ルートを当然ながら優先というか、第一とした上で、もし小浜ルートの今後の整備が困難な場合、本当に行き詰まった時は、米原ルートを検討すべきだと発言をしたという報道がありました。この富山県知事についても知事はどのように受け止めていますか。
[知事]
今申し上げたことと同じだと思います。新田さんの方がもっとというか冷静に客観的に見られてお考えだと思いますが、今の前提そのものが、小浜・京都ルートができないのならというのは当然の話で、どこか考えるしかないわけで、他があるのかどうかはともかくとして、そこのところを言われているのだろうと思いますが、もう基本はとにかく早く小浜・京都ルート。もちろん早くというのは日程を切って何でもやみくもに早く認可・着工してしまえという意味では全くございませんので。これは沿線の各自治体、住民のみなさんのご理解を得ながら、丁寧に説明をして、科学的な根拠も示しながら、説明をしながら前に進めていくということを求められているのだろうと思っています。
[記者]
最近、米原ルートという言葉が、さも存在するかのように、あちこちから出てきて、よく考えてみると、そもそも米原ルートというのはこれまでの検討のなかでないと。小浜ルートに決定したのと同時に米原ルートというのは存在しないルートのはずなのに、こうやって出てくるということで、そういった発言をすることは非常にインパクトがあると思います。彼らは実際には小浜ルートなんだと言いますが、米原ルートというものを検討すべきだという発言は、重いと思います。改めて、沿線の10都府県で作る促進同盟会の会長として、少なくとも北陸の両知事に米原ルートという発言はもう控えてくれとか、我々も小浜一本でいきましょうと、足並み揃えましょうというようなことはお伝えしないでしょうか。
「知事」
ことあるごとに、物事というのは、常に人がどう考えるかということで自由ですので、どう発言するかということも、ある意味政治の自由だったり、思想信条の自由なので、そのことを止めるというようなことは誰にもできないと思います。そういう中で私の思いだけを言えば、米原ルートなんて言わないでくれということはあるかもしれませんが、ご案内の通り石川県内の政治情勢とかいうことを考えれば、馳さんの立場もあり、また沿線の市町、府県にとってみれば住民のみなさんのいろいろなご意見があるかもしれない。そういう中で国として小浜・京都ルートを決めて、今それを進めようとされている、我々もそれを求めている。ですから、私どもはなんとか結果として小浜・京都ルートを一日も早く認可・着工して、一日も早く新大阪までつないでいく、これのために大切なことをやっていこうと考えています。
[記者]
国交省と鉄道・運輸機構が25日に京都府内で、京都府と市町村に向けて、新幹線についての説明会を開くということになっています。京都の懸念がご案内の通り、地下水だったり建設残土の問題、渋滞の問題とたくさんあって、地下水一つとっても、シールド工法という工法で果たして本当に地下水に影響が出ないかというところは、国と鉄道・運輸機構は出ないというものの、本当なのかという声も結構強まっているのも実際で、福井県民としては心配している部分もあります。
説明会がありますが、知事はこの説明会、今後のいろいろな説明の中で、京都の理解は得られていくのだろうかというところ、知事はどのように改めてお考えですか。
[知事]
これまだ1回目が開かれていないので、みんな何か心配になるということだと思います。やはり工法がこうであるとか、過去の実績がこうであるとか、そういうところを科学的にしっかりとご説明をいただいて、進めていく。それこそ日本の科学の粋、技術の粋を集めてこの北陸新幹線は建設促進されていくわけですし、またいろいろな課題がいつでも出ると思いますが、それを乗り越えられるように、英知をまた結集するということも大事なのだと思いますので、私はまず緒につけるということはとても大事で、これは大議論になるかもしれません。しかしそこからどのように解決していくのかというのは、また次に大きな大事なことでして、いつかというか、それをできるだけ早く理解を得ながら進めていけるようにしていくことが大事だと認識をしていますので、政府・与党、そして鉄道・運輸機構のみなさんに対しては、そういったことを丁寧に、しっかりとご説明をいただくことが第一だと思っています。
[記者]
同盟会の話で、今後、概算要求とかに向かって要望活動をまたしていくと思いますが、またたらればと言ってしまったらそれまでになりますが、馳知事とかのおっしゃっている、仮に京都が納得せずに小浜ルートがダメになった場合に、米原ルートを検討するという話が同盟会の中で上がってきた場合、可能性はないとはいえないので、そこは同盟会長としてあくまでも京都に理解が得られなかったとかいう話はなく、これまで通り小浜・京都ルートを推進していくのだというところで一致を目指していくのかどうかというところをお伺いします。
[知事]
まさにたらればというか、悪い状況になった場合のまとめ方とかいろいろ言っていたら、想定問題が山のようにできると思いますが、いずれにしてもみなさん、しかし本当に聞いている限り、一日も早く乗り換えなしで大阪へつなぐということはみなさんおっしゃっていますので、それに今の小浜・京都ルートだと今後どうなるかというところで疑問を持つ人がいるということだと思いますので、同盟会として一致点を見出して、引き続き一日も早い大阪への全線開業、乗換えなし、こういうことをしっかりと小浜・京都ルートでということですが求めていける体制にできるのではないかと思っています。
[記者]
新幹線と話が変わりますが、先ほど知事の話の中で次に大事なイベントとして中部縦貫道という話もあったと思いますが、全線開業の時期とかについては、国の方から何か具体的に目途を持って話を聞いているのか、現状を含めどのような認識で今いらっしゃいますでしょうか。
[知事]
これはまだないです。年度内に次の竣工目標を聞かせていただけるということになっていたと思いますが、年度末が近づいていますので、いずれお話がいただけるのだろうと思っています。
[記者]
年度内ということとなると、そんなに時間もないのかなと思いますが、具体的にだいたいどの辺でという話も知事の方にはまだないのでしょうか。
[知事]
私は聞いていません。事務的にはやっているのかもしれませんが、いずれにしても早めに、作業が遅れているのかもしれませんが、また確認しながら進めていくということかと思います。
―― 了 ――
関連ファイルダウンロード
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kouhoukoucho@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
知事公室広報広聴課
電話番号:0776-20-0220 | ファックス:0776-20-0621 | メール:kouhoukoucho@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)









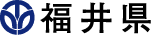


 20250318資料(令和7年度組織改正・人事異動について)(PDF形式 5,347キロバイト)
20250318資料(令和7年度組織改正・人事異動について)(PDF形式 5,347キロバイト) ダウンロードはこちら
ダウンロードはこちら