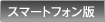知事記者会見の概要(令和6年5月24日(金))
令和6年5月24日(金曜日)
10:30~11:35
県庁 特別会議室

[知事]〔配付資料:北陸新幹線福井・敦賀開業2か月間の状況 〕
北陸新幹線の開業後2か月が経過しましたので、現状について、ご説明をさせていただきます。まず全体的な状況としましては、1か月経ち、2か月経ってきていますが、開業時に比べ、少し落ち着いている部分はありますが、さらに堅調に、順調に来ているというふうに考えています。2か月間の関東圏からのお客様はトータルで5割近く増えているということと、全体でも3割増えております。1か月目と2か月目を比較しますと、少し落ち着いているように見えますが、一方で、ゴールデンウィークは、昨年と比べて日の並びが良くなかったというところがありまして、全国的に見るとマイナスという状況がある中で、2か月目のところはさらに20%以上増えておりますので、そういう意味では、非常に健闘していると理解しているところです。いつも申し上げますが、新幹線で関東から直接来られるようになったということもありますが、いろいろなところで「福井、福井」と取り上げていただいている効果が現れているということで、実際の新幹線の利用者を、昨年の特急に乗っていらっしゃった方々との比較でみましても、開業1か月で26%増えていたものが、ゴールデンウィーク期間中、ここは全国的には人数が減っているのですが、北陸新幹線金沢・福井間は18%増えているという大きな効果が出ているということです。また、消費についても後ほどご説明しますが、入込客は大きく増えている。芦原温泉は、昨年の数値がありませんので、新幹線の開業前と比較して1.6倍と、非常にお客様の数も多いと伺っています。
それから各観光地の状況ですが、恐竜博物館は、昨年は閉じていましたので、コロナ禍前の過去において一番多かった年との比較におきましても、12%増えています。ここのところは、一つ留意点がありまして、もともと平成31年までは、どれだけの人数でも入れていたので、ゴールデンウィークの時には一日に1万5千人や6千人が入って大渋滞になっていましたが、コロナ禍以降、一日1万2千人に制限しています。そういう意味では、夏休みや、ゴールデンウィークは逆にお客様が減ります。そういう仕組みになっている中でも12%増えているというのは、非常に強力です。ご覧いただいてお分かりのとおり、特に平日が2倍以上になっています。申し上げた状況の中で、ゴールデンウィークに人出が少し抑えられていて、土日は9割台と10%減っている中でも12%増えているという状況になります。朝倉氏遺跡も堅調に増えていますし、その他の観光地についても、特に敦賀が終着駅効果もあってということかと思いますが、赤レンガ倉庫が5割近く増えているという状況になっています。
それから宿泊施設、これはFTASといって、いくつかの主要な施設、ホテル、旅館と協力しまして、リアルタイムに人数の確認ができるようにして、比較をしています。これは、昨年10月から始め、去年の数字がないので、開業前後で比較すると、2か月間で5割増えて、6割、4割、5割と増えています。ご覧いただきたいのは、1か月目と2か月目の比較で、2か月目の方が伸びてきているということでして、開業時の一時的な効果というよりは、だんだんと福井が認知されて、みなさんにお越しいただけている。このグラフからも明らかと思っています。そういうことで、芦原温泉も、関東からのお客様の割合が前年の2倍、福井の駅前がビジネス客、観光客両方多いですが、稼働率が非常に高い、越前町でも上がっている。敦賀も満室状態。小浜でも効果が出ているということです。
二次交通の状況を申し上げますと、これも定期利用以外のところ、例えば、普通切符やICカード、フリー切符など、これらを活用した非日常というところを中心に大きく伸びていまして、まず新幹線が来て、特急がなくなって、例えば、福井・敦賀間などは新幹線に乗るかというと、そこから一部、お客様がハピラインにも来ているということもあって、ハピラインが大きく、5割近く伸びています。えちぜん鉄道は、例えば、恐竜博物館、三国港、永平寺など、こういった観光地を多く抱えていますので、これも非日常が大きく伸びています。そうではない、日常利用が多いと思われる福井鉄道でも2割以上、非日常が増えており、日常利用を含めた利用者数でも大きく増えています。また、小浜線・越美北線についても、数パーセント、乗客の数が増えており、これまではずっと下がってきていましたので、それが逆転してきているという状況になっています。
それからバス、タクシー、レンタカーの関係ですが、バスは非常に好調です。土日祝日はご案内のとおり、5月いっぱいまでICOCAやSuicaを使っていただいた場合には、半額ということをやっています。その効果だけかと思いますと全く違っていまして、増減ですので、110%ということは2.1倍になっています。96%というのは4%減ではなく、1.96倍になっているということで、平日も増えています。こういったことで、ICカードなどの活用というのも非常に効果が上がっているとも考えていますし、二次交通としても活用されていると。観光バスについても、まだ活用が少し低調なところもありますが、それでも最初の1か月に比べて2か月目、それから実証運行の時に比べて1.4倍、1.8倍と、徐々に増えてきている状況です。タクシーについても、乗られる方の数というのはそれほど増えていないようですが、運賃収入は25%増と大きく伸びています。料金の改定は昨年末に行って15%上がっていますが、それ以上に伸びている、客単価が増えているということでして、やはり観光利用というのは遠くまで乗っていただけるというところです。レンタカーについても、福井駅前でも5割増えているということですが、その他の地域も増えてきていると伺っているところです。
それから商業施設の利用状況も、くるふ福井駅、これは去年と比較はできませんが、私も参りましたが、ゴールデンウィークもすごい人だったと思います。西武福井店にもお客様が一定程度流れています。それから福井駅以外の芦原のアフレアや、道の駅越前たけふ、敦賀市の駅前、こういったところにも多くのお客様がお越しになられている状況になっており、敦賀のоttaはお客様が2倍になっています。主要なものを売っているところで言いますと、駅前商店街や、それから神楽商店街があります。人出はその両方を見てみますと15%程度の伸びですが、売上は2倍から4倍になっていると伺っていまして、いつも来ていらっしゃった方々も目的があって、どこかで何か買い物をして帰るのでしょうが、観光客のみなさんはいったん来られて、いろいろなところを見て、次々と買っていただいている、そういう状況もよく見えるというところかと考えています。
~質疑~
[記者]
発表事項としてお話になったように、福井という知名度の広がりを示しているデータだということですが、この後、お盆や娯楽シーズンの秋などに向けて、さらにその広まりを維持するための取り組みや考えていることがありましたらお聞かせください。
[知事]
一つは、もうすでに22日から始めさせていただきましたが、ふくいdeお得プレゼントキャンペーンになります。ちょうどゴールデンウィーク明けから夏休みまでの間にどうしてもお客様が落ち込むということもあるので、県単独事業として、ご応募いただいたお客様のうち、概ね半分の方にその場で何か当たると。はぴコイン1万円が当たるとか。まあこういうこともある。また、越前海岸の民宿のみなさんには、全員何かもらえるというようなキャンペーンをしています。伺っていますと、秋の予約とかがどんどん入ってきていて、例年に比べても非常に多いとも伺っていますが、これから例えば、JTBさんは北陸のキャンペーンをやっていただいていますし、10月から12月にかけてはデスティネーションキャンペーンもあるわけでして、これからさらにお客様は福井を目指していただけると確信をしています。これに向けて必要な、例えば、二次交通が少し足りないなどというようなことがあれば、そういったことについても、臨機応変に対応していきたいと考えています。
[記者]
先ほど話のありましたふくいdeお得プレゼントキャンペーンに関連しての話について伺います。宿泊施設や宿泊客の方にお話を伺うと、まだ認知度に課題があるのではないかと思います。知らずに来たという宿泊客の方も多かったので。そこが宿泊の喚起に今具体的につながっているのかというと、疑問が残る部分があるかと思いますが、この一般的に夏休みまでの閑散期と言われる時期に、もう一つのキャンペーンとして、今後の認知度拡大のためにこう何か対策など考えていますか。
[知事]
これはおっしゃるとおりで、いろいろ県は考えて事業を打っていますが、PRが弱いというところはあると実際思っています。いずれにしても、知らなかったという人がいたということは、大きく反省すべきことですが、逆に言うと知っている方もたくさんいるということなので、知らない人をいかに減らすかということは、やはりこれは県内に来られる前からいろいろな発信の仕方の強化をしないといけない。県内ももちろん知っていただくことで、県が公表するだけではなくて、旅行会社さんや宿が、いろいろな形でそういうPRをしていただくという効果も非常に大きいので、そういう意味では、県としてのPRもこれからさらに強化をしていくということと共に、一緒になって、これによって効果の上がる、みなさんで口コミを含めてということになりますが発信を強化していきたいと思います。
[記者]
二次交通など非常に好調な一方で、気になっているのがはぴバスの利用状況の部分ですが、認知度の部分について課題があるのか、もしくは使い勝手の部分に課題があるのかどのように見られていますか。
[知事]
基本的には、やはり認知度は低いんだろうなと思います。まず一つ、来られるお客様は新幹線を使われる。その上でレンタカーを最初から利用しようとして来られるという方が多いということもありまして、そういう意味でははぴバスに最初から頭がいかないというところもあると思います。例えば東京のはとバスだと、はとバスにどういうものがあるかは知らないにしても、はとバスってあるんだよねっていう思いがあると思います。そういう意味ではぴバスというのがあるということをですね。乗っていただいた方には非常に好評だと伺っていますので、そういう意味では、特に自分で運転をなかなかされないような方にできるだけ訴求できるように、旅行会社の商品の中に組み込んでいただくとか、それからそういった旅行代理店に来られた方に紹介いただくとかいうことはできると思いますので、今回課題も分かってきましたので、こういったところをさらに強化していきたいと思います。
もう一つは来てからも、この場合は半日コースとかもありますので、使っていただけると思いますので観光案内所でも十分にご説明もさせていただく。そういったポスターを貼ったりということもあるかもしれません。まあ、こういったことは、この1、2か月の反省を踏まえてやっていきたい。いずれにしても、ちょっとずつ認知度も上がってきているとも聞いておりますので、夏休みに向けて、さらに秋に向けて活用していただけるように努力をしていきます。
[記者]
ライドシェアについて伺います。とうとう実証事業を行うと公表されましたが、県民への理解をどう進めていきたいか伺います。
[知事]
ライドシェアの場合は、簡単に言えば、電話でタクシー会社に電話かけたんだけど、「今いません」、「ちょっと待ってください」、「一時間待ってください」などというようなことを解消する、お客様の面から見るとそういう部分が大きいわけですので、しっかりとお分かりいただけば、ご理解いただけると思います。そういう意味では、安全性と言いますか、タクシー会社が運営するということですので、車は個人さんの車かもしれませんが、雇われているのはタクシー会社に雇われているということになりますので、もちろんそういう意味では、安心してお乗りいただけるということをご理解いただいた上で、こういう制度で、普通のタクシーではない車が来ても安心なんだよということを分かっていただくというPRも大事かなと思っています。
[記者]
もう一点、ハピラインについて伺います。開業から、夕方の通勤通学時間帯の臨時便を毎月行っていると思いますが、そこに関して、増車・増便などを常設で行うべきと考えるか、それとも臨時を続けていくべきだと考えるかいかがでしょうか。
[知事]
二つありまして、一つは必要に応じてずっとやっていきたいというところもありますし、一方で車両の数が限定されているというところがありますので、現状においては、不足しがちなところにできる限り増便をしていくという手法が現実的かなとは思っています。少し落ち着いてきていますので、あとは本当に臨時に急にたくさん人が乗るという時をいかに見越しながらやっていくか、こういうことが中心になると思います。また長期的な観点からは、すぐに手に入る車両もないということも伺っていますが、長期的にはそうした常設で、常にこう増やさないといけない時間帯があるとして、他に車両がなければ買っていくということも、長期的にはあり得るかと思います。ただ、今は、増便をできるだけ工夫しながらやらせていただこうと考えています。
[記者]
ハピラインについて追加で質問させていただきます。以前の話で出たとは思いますが、敦賀駅にてJRの在来線からハピラインに、もしくは新幹線からハピラインに乗り換える場合に、切符売り場がなかなかどこにもないという問題が以前からありまして、利便性確保という点でも、あと無人駅で降りる場合に、考えたくはないですが、料金を支払わずに降りてしまう方が一定数いるのではないかという恐れもありまして、この現状について知事としてどのように受け止めているかどうかというのが一つと、今後の対策について何か考えていることがありましたらお願いします。
[知事]
基本的にはキセル乗車、払わないで乗れば無賃乗車ですが、これは犯罪ですので、しっかりとご認識をいただきたいと思っています。一方でおっしゃっていただいたように、であればきちんと払える場所に、もしくは自分がそこを通ったということを、先に入場の記録がないから出場ができないという話になりますので、そのところをきちんと制度的にやって欲しいという声もあるわけです。
遠くまで行くことになると、ICOCAが使えないということにもなりますので、周知をまず良くさせていただこうと思います。大阪ぐらいまでの今まで特急が停まっていたような駅、それ以外も大阪市近郊のところは降りられたりするのですが、制限があるということは交通系ICカード一般に言えることで、例えばSuicaがJR東海のところまでは乗って行けないなど、そういったことは他にもありますので、利便性はそういったことがあるというご理解をいただくことのPRをこれからもやっていこうと思っています。
そのうえで、やはり本質的には、新幹線の駅を降りたらすぐハピラインに乗り換えるところの間なのか、もしくはハピラインに乗る直前のホームなど、そういった場所もあると思いますが、このところに入出場のチェックができるような機器を置くことが本質的な解決策だと思いますので、一つには、一回外に出ていただいて、入場・出場の記録をきちんとやってくださいということと共に、この話はJRとともにさせていただいています。方向としてはやっていく方向に徐々に進んでいると思っていますが、まだ決まっておりませんので軽々には言えないですが、できるだけ急いでやっていきたいと思います。しかしJRも機器がICチップなどいろいろな部品が足りないと言われている部分もあるそうですので、こういったところを前向きに、早めに解決できるようにしていきたいと思っています。
[記者]
間もなく出水期を迎える時期に入ると思いますが、水防訓練も予定されているということで、去年は越前町で、一昨年は南越前町で大雨がありましたが、今年の出水期に向けて、災害対策への姿勢や、もしも何か新しい対策などなれば一言伺えればと思います。
[知事]
対策として、私たちはできるだけハザードマップなどの整備を各市町にもお願いして進めていただいていますが、徐々に充実されてきています。ただ、基本的には降ってきてしまうことを事前の段階で、今の段階でも訓練は各地域でやっていただきたいです。総合防災訓練や今回の水防訓練も間もなくやらせていただきますが、大きな訓練も大事ですが、いつも申し上げていますが、地区で、例えばもしもの時にはどこへ逃げるのか、もしくは避難所の鍵は誰が開けるのかなど、こういったことをまずは地区で話し合ったり、もっと言うと各家庭でよく確認をしておいていただくということが実は一番重要だと思っています。ですので、こういったことを出水期に向けてPRをさせていただこうと思っています。あとは起きてしまった、もしくは起きる直前、特に雨の場合は全く降らないと思っていたところが土砂降りになって何か起きることはあまりありませんので、事前から来そうだということはみなさんお考えになると思います。もしも足の具合が悪い方がいらっしゃるのであれば、早い段階からで逃げていただくなども必要だと思います。ですから、みなさんにもぜひ直前のいろいろな天気予報や、また県や市町からの広報にも耳を傾けていただいて、いつでも動作できるような体制にしていただきたい。こういったことの広報も強化をしていきたいと思います。
[記者]
北陸新幹線の同盟会の冒頭で、知事から敦賀以西の推進は原発立地地域の振興にもなるという趣旨の発言がありましたが、今後、敦賀以西の建設を推進していくにあたって、原発の立地地域であることも交渉材料の一つとする方針ということでよろしいでしょうか。
[知事]
これまでも原子力立地地域の振興ということで、特に今は原子力基本法が改正になって国にも事業者にも立地地域の振興というのが責務になっているわけですので、そういった話の中でこれから地域振興として、いわゆる各市や町が個別にこれが必要だと考えている地域振興の他に、嶺南地域大でものを考えたとき、もしくは福井県大で考えたときに大きなものとして北陸新幹線であったり、それからまた舞鶴若狭自動車道の4車線化ということはあるということでこれまでも申し上げてきました。
ただ、今回もつくづく新幹線が開業して嶺南地域のみなさんの反応を見ていると、早く小浜に来てほしいということをみなさん強く意識をされるようになったと思っています。これからもさらに強くこの原子力、今全国で12基原子力発電所が稼働していますが、そのうちの7基は福井県ということですし、安定して電力が供給されている、それからまた関西地域はご案内のとおり日本で一番安い電気料金になっている、そういうことで企業なり個人のみなさんも潤っている、発展しているわけです。関西地域とこの原子力の立地地域というのは一連であるという意味でも象徴になるわけですので、北陸新幹線は原子力立地地域に必要だということの思いを強く訴えていくことは、これから重要だと私も認識をしています。
[記者]
新幹線敦賀以西について何点かお尋ねします。先日の同盟会促進大会では、私も現地にいたのですが、杉本知事の小浜・京都ルートに対する強い決意を感じました。その後、各省庁、要請活動に行かれましたが、基本的に非公表で行われたのですが、その中で各省庁や与党のみなさんとどのようなやりとりがあったのか、25年度の着工に向けまして、例えば詳細ルートや予算の見通しなど中身がどんなやり取りがあったのか言える範囲で教えてください。
[知事]
一つには、これから敦賀新大阪間の整備委員会が開かれていくと思いますが、委員長を予定されていらっしゃる西田先生があの場でも言われておりましたが、さらに力強く、これから整備委員会をいずれ開いていくという時に、米原ルートの話もありましたが、そういったこともこれまでどのような経過でそうなったかということをきちっとまず確認をした上で議論を進めていって、一日も早く駅の位置やルートも明らかにしていく、財源の議論をしていくと力強くおっしゃっていただきました。
また一番印象に残っているのは、やはり斉藤国土交通大臣、そして村田鉄道局長のところです。ルートというのは、今やっている検討というのは一体どこを念頭に置いているのですかということをお尋ねしたら、小浜・京都ルートのみを念頭に置いて、例えばアセスであったり、事業推進調査を行っているということを力強くおっしゃっていただいて、できるだけ早く詳細ルートを明らかにしたい、一日も早く全線開通させたいということを強くおっしゃっていただきましたので、とても心強く思ったというところです。
[記者]
重ねてなのですが、今与党が目指しています時期としましては、来年度の認可着工であるということを考えますと、知事とされましては、駅位置と詳細ルートの公表時期がいつまでも後ろにまわしていては認可着工に間に合いませんので、知事の思いとしましては、例えば何月頃までには公表していただきたいなど、スケジュール感のお考えというのはございますでしょうか。
[知事]
具体的に頭でイメージをしますと、来年度中には認可着工ということを描きますと、今年の年末には着工できる予算が計上されていないといけません。そうしますと、8月の概算要求の時には何らかの形で着工予算に結びつくような予算の要求がされていなければいけないので、その前の段階として駅の位置、詳細ルート、事業費等も一緒になって出てくると思いますが、そういったものが明らかになっている必要があると思います。そういうことから考えれば、私がいつということを技術的には申し上げられませんが、今言った日程に従う範囲で、年末までは出ていないとできないということだと思います。今回もその方向で求めたということです。
[記者]
最初に質問があったライドシェアについて改めてお伺いしたいのですが、知事は先ほど安心安全面でご発言いただきましたが、実際、今回のこのメリット、特にタクシーの利用客がそこまで伸びていない中でライドシェアを導入することがどんな効果をもたらすのか、そしてこれからドライバーの募集など始まると思いますが、どの程度の規模を県内で見込んで展開を図っていくのか、そのあたりの展望も含めてお聞かせください。
[知事]
新幹線が来てお客さんはいるのに車がないという、少し前まで一番大きく心配をしていたことは、ある意味おっしゃるとおりでして、それは今のところ一定程度落ち着いてはいるということです。一方で、県内は今回9社が手を挙げられまして、この中身を見せていただくと、例えば全日、一日中足りないという事業者もいますし、特に週末もしくは夜間の部分に手を挙げてこられているという事業者もいらっしゃいます。それぞれ見ますと、やはりそれぞれの企業にとっていろいろなパターンがあって、その理由は先ほども申し上げましたが、「電話がかかってきても車がないんです」ということが、結果としてある時間帯があるということだと思います。トータルで足りているように見えても、やはりスポット、スポットで足りないというところを埋めていくのはこの事業だと思いますので、そういった意味での効果は大きいと認識しています。そのうえで、これから夏目途ということで実証事業を始めていただくということですが、その中で課題等があればいろいろと考えていただく、解決策を考えていく、こういったことになろうと思いますし、またこれはお話をしていると、物理的に車が足りる・足りないということだけではなくて、このライドシェアで自家用車を使って、言ってみればアルバイト的に運転をやっていくなかで、「タクシー面白いんじゃない」と言って今度正規の方になっていただくということもあり得るのではないかというようなことも、お考えになられている事業者もいるようなので、いろいろな効果が期待できますので、言ってみればタクシー会社さんがやられる事業ですから、安心して、さらにそういった実態がどうなっていくのかを確認するという意味でも、しっかりとこの実証事業を成功させていければと思っています。
[記者]
玄海町長が核ごみ処分地の文献調査受入れの考えを表明しました。北海道の地域に続いてということになるが、電源立地地域としてこうした受入れの表明が広がったことへの受け止めと、核燃料サイクルへの知事の考えを改めてお聞きします。
[知事]
町内において熟慮されて出された答えだということなので、私から他の自治体についてコメントするということは控えさせていただこうと思います。
ただ、一方でこのバックエンドの課題というのは、これは電力の恩恵を受けているすべての国民の皆さんが等しく考えていかなければいけない課題だと思っています。そういう意味では、これは決して、今回で言えば玄海町だが、そうした手を挙げたところだけの課題のように集中的に取り上げられるとこういうことではなく、国全体で考える、そして国が前面に立ってこれを解決するように努力をしていく、こういうことをぜひお願いをしたいです。すぐにメディア的にも矢面に立つような形になるということがないようにして、このバックエンド対策をみんなで考えていかなければいけないと考えているところです。
[記者]
高レベル放射性廃棄物の処分場についての県のスタンスを伺います。前回の会見でも同様の質問があり、国民全体で考えていくという考えを答えられていましたが、NHK全国アンケートの福井県回答では、処分場を県内で受け入れる考えや、その前段の調査を受け入れる考えの部分が無回答・その他と回答していたとのことですが、そのように回答した背景について伺います。
[知事]
これは、仮定の質問に答えるということはないという趣旨で申し上げています。ということはどういうことかというと、県内で今、市や町の中でそういったものを受け入れるとか受け入れないとか、こういった議論があるわけではないので、そういう意味で県はその後、最初に受けるかどうかは市や町の議論から入るので、そういったことにお答えすることはないと、無回答ということになっているわけです。
[記者]
調査を受け入れるかの入口としては市町村で、処分場を受け入れる際には県の了解が必要になると思います。他県では発電を引き受けているので処分場を受け入れる考えはないとはっきり回答している首長もおり、改めて知事の考えをお聞きします。
[知事]
今回の、NHKであるが、アンケートについての回答として一番適切なものとして、現在県内でこうした議論があるわけではない、市や町で、そういう中で今、仮定の質問に答えるタイミングではないということでお答えをしたという程度です。
[記者]
国のエネルギー基本計画の改定作業が始まり、知事も委員をされていると思いますが、原子力発電所のリプレースについて、新たな計画にどのように位置づけられるべきだと思われますか。
[知事]
どう位置付けるかは、いろいろな議論の中で決まっていくと思っていますが、まず私どもが常に申し上げているのは、リプレースに限らず、これに結びついていく方向として大事なことは、安全安心に向けて、新たに原子力発電所を作るということの安全投資の部分を十分可能になるような枠組みが第一に重要だと考えています。
さらに言えば、既設炉にせよ新設炉にせよ安全投資が可能である、ここが大事なうえに、そこに向けてどんな手順でいくのか、こうしたことも明らかにしていかなければ、絵にかいた餅になっていくわけなので、そうした必要性があるというのであれば、安全性をどう担保する枠組みを作るか、そしてどういう手順でものが進んでいくようにするのか、こうしたことについて明らかにしていく、その議論の場所になっていくのかなと思っているところです。
[記者]
関西電力は福井県内でのリプレースに意欲的で、美浜町の町民からもリプレースを期待する声もあがっています。一方で、リプレースに向けては手続きの面とかファイナンスとかいろいろな課題があると思いますが、地元の期待の声と実現に向けた課題について、知事はどう思われますか。
[知事]
これは、まだまだこれから、立地地域だからというのは強くあるかもしれませんが、常にいろいろな声があると思います。リプレースに限らず、積極的に原子力産業を発展させるべきだという考えもあれば、安全最優先ということからいえば、不安があるという声も強いわけです。こうしたところは、国や事業者が進めるということであれば、先ほど申し上げたような課題も含めて、十分に説明していただいたり、反対されている方もしくは不安に思われている方に対しての説明も十分にする、こうしたことを、それぞれの立場でしていくというような段階ではないかと思っています。
[記者]
エネルギー基本計画について、15日に議論が始まったところで、知事は公務の関係で意見書を提出されたところだと思いますが、脱炭素化の柱として原子力、再生可能エネルギーを挙げられています。この部分について今回の見直しの議論で主眼において考えられていることを改めてご説明いただきたいです。
[知事]
今回のエネルギー基本計画の大きな柱は、いかにして脱炭素を進めて行くのか、それに向けてエネルギーミックスであったり、GXや省エネとか、量を使わないことももちろん重要なので、こうしたことが1つの大きな柱になると理解しています。
脱炭素という意味では再生可能エネルギーもあり、これについて特に福井県の関心事項としては、全国的にもあるような環境破壊への対応ということももちろんあります。その上で、蓄電池の活用。系統の中に蓄電池をしっかりと位置付けていくということは再エネの活用について負荷を減らしていくことにも繋がるし、災害対策にも非常に大きな良い方の材料にもなっていくと認識しています。そういった再エネの導入に向けては、通常の他にこういった蓄電池の活用もあると思います。
また原子力については福井県の場合は、日本最大の立地地域でもあるということであると思います。そういう意味では、これまでも申し上げているが、原子力発電、必要な、今は20~22%ですが、できるだけ低減していくと、こういうわかりにくいことになっていますが、一体どの程度いるのか、そういった必要な規模と、それからもう1つ言うと、2040年を過ぎてくると一気に原子力発電所の数が減っていく、こういう状況の中でどうやって道筋をつけて、そして必要な量、まだ数%しかないわけですが、こういったものを実現していくのか、こうしたところも明らかにしていただく必要があると思います。
さらには先程から話が出ていますが、バックエンドの対策とか、原子力の防災体制、地域振興、こういったところについても、しっかりと新しいエネルギー基本計画の中で明らかにしていただく必要があると思います。
もう1つ脱炭素という意味では、水素のことも非常に大きな課題になってくると思っています。水素については大きく言うと全国で8カ所、そういった水素の供給拠点を作って、そこを応援していくんだというのが今のところの国の見解だと思いますが、ここのところは、単に供給拠点が8カ所あればいいのだろうかということは非常に危惧している。やはりいろんな国土の中で、今回の能登半島の地震もあったが、南海トラフ地震ということも具体的に言われているわけであり、そういう意味ではお互いに、日本海側と太平洋側が融通できる、8カ所が点で存在するのではなく、線でちゃんと結ばれているということの必要性が非常に高まっていると思いますので、こうした水素も含めて、国内での強靭化、国土の強靭化ということを含めて、しっかりエネルギー基本計画の中でも考えていく必要があると考えています。
[記者]
知事は、よく原子力の将来像を明確にという言葉を使われますが、今の発言からすると、2035年以降の電源構成を見据えての話もそうだし、2050年の脱炭素化というところも踏まえてのことだと思いますが、将来と言ってもいろいろな見方ができるので、このあたりの想定をどのように考えているのでしょうか。
[知事]
具体的な時期をいつにして、量をどうするかということは、まさにこれからエネルギー基本計画の議論の中で考えていくのだと思います。
原子力の将来像と言っているのは、中を分解すると、ある時期というのがいつかは分かりませんが、それは決めていただければよいのですが、ある時期における必要な規模とそこに至る道筋、こういったことを明らかにしなければいけないのではないかということです。
[記者]
先ほども質問が出ていた敦賀以西に関して、西田委員長が新しい駅の話をしてはどうかというようなことをインタビューに答えられていたことがあったと思いますが、実際にルートを大きく変えるということではなく、京都にもメリットのあるような場所に駅を設置することなど、一定程度、計画の見直しを受け入れやすいような形で行うという方法も考えられると思いますが、計画を作るのは県ではないですが、そういったことの仲介や提案など、今のまま前に進めるということ以外に何か考えがあればお聞かせください。
[知事]
おっしゃられていることについては報道等で私も認識をしています。しかしルートの問題は、とりあえず現状においては小浜・京都ルートで、駅は小浜から京都に行って、松井山手のところを行って大阪につなぐということで決まっていると思います。もう一つの要素として言えば、今回の要請事項の一つにもありますが、効果に応じた費用負担というか、費用に応じた効果というか、こういったことを求める声があることは間違いがありませんので、そういったことにどう応えるのかというような議論の中で、そうしたことが議論されるということは考え得ると思っていますので、このところはまず議論を拝聴させていただきながら経過を見て、我々としてもご意見を申し上げる必要があれば申し上げていくということかと思っています。ただ大きく言えば、いろいろな考え方はあると思いますが、今の案に従ってやっていただければと思っています。
[記者]
昨日の5月23日、敦賀市議会で説明がありましたが、人口減少の本当の原因を探ろうということで、一からデータなどを見直すという動きが敦賀市であります。人口動態の解明となると、なるべく広い範囲でやった方がより正確に、特に社会増減なんかに関しては、実態がつかめるのかなとも思いますが、本来、国全体でやるのが一番いいんでしょうけれども、こういったことに県も歩調合わせて、より広い範囲での解明に協力するなど考えがあればお聞かせください。
[知事]
今、敦賀市さんがされている一つ一つのことをどうこうするかについて、個別にまた考えさせていただきますが、福井県も今年度、人口減対策の5か年計画を見直す時期ですので、いろいろな調査等もさせていただこうと思っています。ただ本質的には、私はいろいろなところで申し上げていますが、国全体では社会増減ゼロなわけです。もちろん海外に行く人はいるから、それはゼロとは言えませんが、ほぼゼロなわけです。だから、国はあまり興味を持たれてないように思って、地方創生の枠の中で、しっかりと地方創生を図っていただいて、若い人を集めてくださいよというようなことで終わってしまっているということが問題だと思っています。社会増減の問題もまさに自然減の問題に直結しているといつも申し上げていますが、福井全体で、社会減2,600人のうち1,800人は20代です。この時の20代というのは、18歳の部分も含んでいます。だいたい大学を出て就職するときに住民票を移す人が多いので、7割以上は、結局、就職もしくは大学へ行く時に人が減っています。それに対して、東京圏の一都三県の人の増え方の9割は、20代の時の移動です。ということは、結局、大学行く時、それから就職をする時、これをどうするかというのは非常に大きな課題です。これは何も福井県の課題というよりは、例えば、大学の入学者、福井県の場合は大体3,900人ぐらい大学に行きます。でも、福井県内の大学定員は2,330人しかない。1,600人はどう考えても出ていかないといけない。しかも、出て行ってしまった人たちのうち数百人は、できれば福井にいたかったと言っているわけです。東京に18歳の高校3年生の人口は9%しかいないのに、大学1年生の東京都における人口比は全国の25%す。9%しか高校生はいないのに、25%集めるわけです。こういう制度を国がやらなくて、都道府県が頑張ったところでどうにかできるわけではない。結果として、福井県に、1980年代生まれの人たちは、西暦2000年の時には10代で、9万4千人いました。20年後の2020年になって、同じ1980年代までの人は30代になり、7万9千人の16%減となっています。それに対して、東京都は、112万人が196万人になり75%増えています。この20年間で1980年代生まれの人が、福井で16%減って、東京都では75%増えているわけです。これはまさに人口構造そのもの、社会の構造そのものを見直さないといけないのであって、福井県が東京都と戦うとか、そういう問題とは全く違うと思います。結果として、合計特殊出生率は、福井県が1.50、東京都は1.04ですが、3分の2しか生まれないところへどんどん人を増やしているわけです。特に、この20年間で75%も増やしてしまっているわけです。これは国策としてどうしますかということを、先日も将来世代応援知事同盟の中で具体的に申し上げさせていただきましたし、具体的な方法論についても、これまでも申し上げていますが、これからもしっかりと国の方には訴えていきます。その中の、今おっしゃったデータの部分は非常に重要だと思います。まず国が本気になってやっていただく必要がありますが、今も申し上げたような数字も含めて、我々として把握できることを明らかにしていきます。
今やっている私たちの人口減対策は何かというと、大きく東京に取られていて、大阪も、札幌も、仙台も、大阪も、名古屋も、福岡も、全部東京に取られています。東北のみなさんは仙台にいっぱい集まります。集まった上で東京がとっていきます。これはおかしいです。これで人口を減らしているんだから。これはなんとかしないとどうするんだということです。だから大学の定員についてですが、平成30年の時に、十年間は東京の定員は増やさないということを言いましたが、平成30年から令和5年までの間に、大学へ行く子どもの数が全体で0.5%増えましたが、現実に東京に行った子どもの数は、3.2%増えています。抑えると言っておきながら0.5%増えている中で、3.2%東京が持ってってるわけです。効果がどうなっているのかと、こういうことの検証も必要だと思います。人口減対策として、今、私たちがやっていることは、大きく東京に取られた上でのマイナスサムの中での競争を強いられているわけで、これは単なる消耗戦です。もっと国策として、人口減対策というのは考えていただく必要があります。先日、人口問題の提言がありましたけれども、非常にいいきっかけだと思いますので、今度の全国知事会議でも、主要な課題の一つになると思っています。
[記者]
関連で、東京一極集中の問題点だと思いますが、その反対となると多極分散ということになります。知事の考えとしては、例えば、大学を地方に持っていくとか、省庁を地方に持っていくとか、いろいろなやり方があると思いますが、どうお考えになられていますか。
また、全国知事会が7月末にありますが、そういう東京一極集是正に向けた何らかの議論を、福井県がリードしていくということはありますか。
[知事]
全国知事会議は、全国知事会としてどういうふうにやっていくのかですが、一つの議題になるとは思っています。東京一極集中という言い方にするのか、人口減、社会減をどのように解決していくのかといったもう少し幅広い観点にするのか。というのは、消滅可能性自治体というような言い方もされてますが、これは地域の問題でもありますので、そういったことをどう解決するかといったもう少し幅広い観点かもしれません。ここは全国知事会の中で、よく議論していただく。本県は、全国知事会議を開催いただく県ですので、運営については全体で議論しながらやっていくのかなと思っています。
具体的に、どうやって社会増減の課題を解決していくかというと、私どもが申し上げているのは、一つは先ほど申し上げた、大学の定員を人口の比率に合わせたような形にしていくことが、少なくとも福井県においては、今でも福井に残りたいのに残れない人がいっぱいいる。福井県の場合は、大きく言うと県内の大学定員の半分ぐらいの人が県内からの進学者で、就職のとき8割方は、福井に残ります。そして、県外から県内の大学に進学した人のうち1、2割が福井に残るので、トータルすると半分近くに減ってしまうということです。いずれにしても、大学の定員を増やせば、福井県に残る人の数は増える可能性が非常に高い。一つはそういったことの要請をしていこうということです。
もう一つは、法人税制で、例えば就職するところは、就活を大学の近くですることになっていきますので、なかなかいきなり地方でというのは難しいかもしれません。一方で、会社に入った後、地方にいる従業員の比率の分だけ税額控除を行えば、黒字を出している企業さんこそ、同じ人数の従業員が全国でいましたら、地方に置く方が税額が安くなります。こういうようなことを今訴えてます。そうすると、仕掛けとして、循環していくわけです。しかも、これも法人税のレベニューニュートラルで、税収中立の水準に税率を一旦上げて、今みたいなことをやれば、税収が減るということでもありません。
私が申し上げているのは、お金としては大学移転の経費ぐらいは見てあげるというのはあるかもしれませんが、何十兆円もかけて国土を改造するということとは違い、本気度があればやっていけるということです。例えば、東京の大学が定員100人だったとしたら、それのうちの30、40を地方に転換すれば、その定数は維持してもいいですよというようなことをやっていけば、子どもの数はいるわけですので大学も困らない。いろいろな方法があると思いますが、本気を出すと、そう無茶にお金かけなくても、社会の構造は変えていけるのではないかというのが、福井県が今申し上げている提案です。
[記者]
京福バスの減便を検討している話についてお聞きします。新幹線延伸によって本当に新幹線も好調ですし、二次交通も非日常分野を中心に非常に好調だとは言いますが、その反面で県民の足元を支える路線バスで、運転士不足によって減便が続いていくという、県民にとっては非常に心配な面もあります。県もこういった事業者に対しまして、さまざまな運転士の魅力発信や、あるいは財政的な支援など様々されていると思いますが、今後、さらに減便が予測される中で、県としてどのように対応していくか、お考えがあればお聞かせください。
[知事]
これは本当に大きな課題だと認識をしています。バス事業は元々、非常に公共性が高いということもありまして、いろいろな形で補助金を出させていただいたり、最近でも例えば合同企業説明会を開いたり、運転士が二種免許を取りやすいように補助させていただいたり、こういうこともさせていただきました。ただ、その効果としても、まだまだ足りないということが今回の結果であって、なおかつ今日の報道にもありましたが、まあそうならないことを祈りますが、このままいけば、今後もさらに減便ということにせざるを得ない。こういう状況になっていると思っております。やはり大きいのは、給与の水準が全産業平均に比べても安い。こういうような中で、なおかつ都市部と地方部の差も大きい。ですから、そういった運転免許があれば、なんだったら都会に行った方がもっと儲かる。こういうことも含めてなかなか厳しい。地方のバス事業というのは本当に福井に限らず厳しい環境にあると認識しています。さらに厳しいのは、事業者のみなさんは、まず路線を維持しようとして路線に人を貼り付けていただいています。結果として儲かるべき観光バスが走らせられないから、さらに経営が厳しくなる。給料も上げにくくなる。こういう悪循環に近い状況になっているのかと思っています。こうした大きな課題のところは国もしっかりと、国全体として考えていただきたいということで、これもお願いを強めていきたいと思います。
さらに福井県内の状況で言えば、目の前の、運転士さんを集めないといけないということですので、これについては28日から緊急の対策会議を国、県、市町、事業者、こういった方々と始めさせていただこうと思っています。例えば、説明会そのものは合同でやるだけではなくて、個別の説明会にも支援をしていく、運転士が採用されたら、それに奨励金を出して、少しでも処遇を改善していく、また退職されるタイミングは運転士に限らずあるわけですが、いろいろな方が退職するタイミングというのは、次の仕事を探されていますので、そういった方々が運転士になりやすいような環境、例えば二種免許を取るときの支援をするなどの強化をするなど、いろいろなやり方はあると思いますが、いずれにしてもまず即効性のある対策を打ちながら、少しでも持ちこたえて、本質的に給与の問題とかを含めてこの構造をどう変えていくのかを国と共に一緒に考えながら、我々としても努力をしていきたいと思います。
―― 了 ――
関連ファイルダウンロード
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kouhoukoucho@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
知事公室広報広聴課
電話番号:0776-20-0220 | ファックス:0776-20-0621 | メール:kouhoukoucho@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)









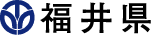


 20240524資料(北陸新幹線福井・敦賀開業2か月間の状況)(PDF形式 1,435キロバイト)
20240524資料(北陸新幹線福井・敦賀開業2か月間の状況)(PDF形式 1,435キロバイト) ダウンロードはこちら
ダウンロードはこちら