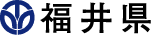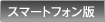食品中の残留農薬等のポジティブリスト制度について
概要
食品中に残留する農薬などが、人の健康に害を及ぼすことのないよう、厚生労働省は、全ての農薬、飼料添加物、動物用医薬品について、
残留基準を設定しています。
残留基準は、食品安全委員会が人が摂取しても安全と評価した量の範囲で、食品ごとに設定されています。
農薬などが、基準値を超えて残留する食品の販売、輸入などは、食品衛生法により、禁止されています(いわゆる「ポジティブリスト制度」)。
また、農薬が基準を超えて食品中に残留することのないよう、農林水産省が、残留基準に沿って、農薬取締法により農作物を育てる際の使用基準を設定しています。
また、食品の輸入時には、検疫所において、残留農薬の検査等が行われています。
農薬の残留基準はどのように決められている?
食品中の農薬の残留基準値は、農薬を定められた使用方法で使用した際の残留濃度等に基づき設定されています。
コーデックス委員会(※)が定める国際基準があるものについては、国際基準も参照されています。
こうして設定した残留基準値については、農薬が残留する食品を長期間にわたり摂取した場合や、農薬が高濃度に残留する食品を
短期間に大量に摂取した場合であっても、人の健康を損なうおそれがないことが確認されています。
具体的には、我が国における各食品の摂取量を勘案して、食品を通じた農薬の摂取量が、
・毎日一生涯にわたって摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量 (ADI:許容一日摂取量)
・24時間又はそれより短時間の間に摂取しても健康への悪影響がないと推定される量(ARfD:急性参照用量)
をそれぞれ超えないことが確認されています。
なお、このADI及びARfDは、動物を用いた毒性試験結果等の科学的根拠に基づき、リスク評価機関である食品安全委員会が
食品健康影響評価(リスク評価)を行い、設定しています。これを受けて、厚生労働省において、上記の考え方に基づき、
薬事・食品衛生審議会での審議を経て、残留基準値を設定しています。
(※)FAO(国際連合食糧農業機関)及びWHO(世界保健機関)により設置されている政府間機関
<参考>「よくある質問 Q1」より(厚生労働省ホームページへリンク)
コーデックス委員会(※)が定める国際基準があるものについては、国際基準も参照されています。
こうして設定した残留基準値については、農薬が残留する食品を長期間にわたり摂取した場合や、農薬が高濃度に残留する食品を
短期間に大量に摂取した場合であっても、人の健康を損なうおそれがないことが確認されています。
具体的には、我が国における各食品の摂取量を勘案して、食品を通じた農薬の摂取量が、
・毎日一生涯にわたって摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量 (ADI:許容一日摂取量)
・24時間又はそれより短時間の間に摂取しても健康への悪影響がないと推定される量(ARfD:急性参照用量)
をそれぞれ超えないことが確認されています。
なお、このADI及びARfDは、動物を用いた毒性試験結果等の科学的根拠に基づき、リスク評価機関である食品安全委員会が
食品健康影響評価(リスク評価)を行い、設定しています。これを受けて、厚生労働省において、上記の考え方に基づき、
薬事・食品衛生審議会での審議を経て、残留基準値を設定しています。
(※)FAO(国際連合食糧農業機関)及びWHO(世界保健機関)により設置されている政府間機関
<参考>「よくある質問 Q1」より(厚生労働省ホームページへリンク)
関連リンク
厚生労働省ホームページへリンクします。
●食品の残留農薬等
●ポジティブリスト制度について(Q&A)
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、iyakushokuei@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
健康医療局医薬食品・衛生課
電話番号:0776-20-0354 | ファックス:0776-20-0630 | メール:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)